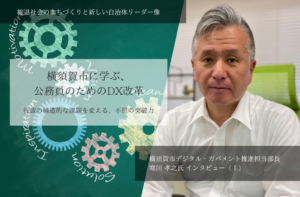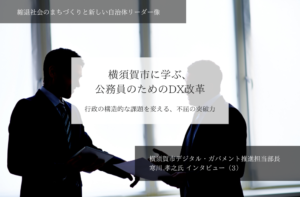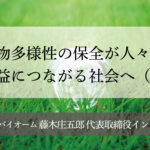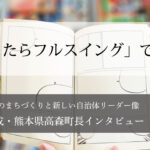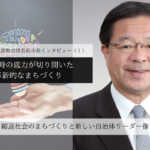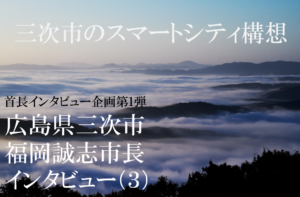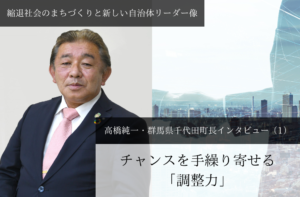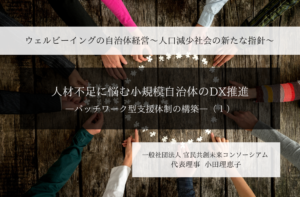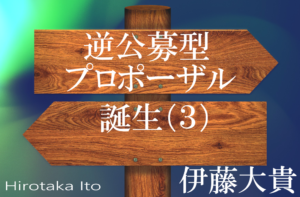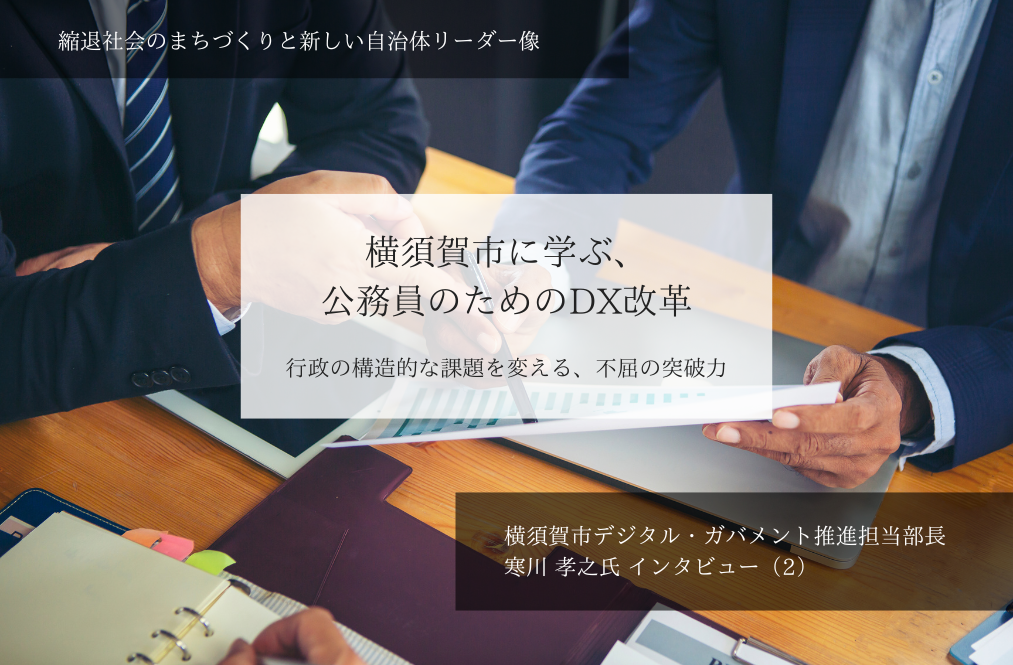
神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長 寒川孝之
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/07/09 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(1)~
2025/07/10 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(2)~
2025/07/15 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(3)~
2025/07/17 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(4)~
議会の役割と過去の経験からの学び
小田 議会が応援してくれるというのは大きいのですか?
寒川氏 大きいですね。議会は我々の取り組みをすごく評価してくださり、一般質問で応援してくださったりもしました。否定的な質問ではなく、「こういった取り組みは素晴らしいと思う」「こういった部分をもっと発展させることを考えませんか」といった前向きな質問をしてくださります。
小田 ちょっと目から鱗です。このテーマで議会対応のことは聞こうと思っていませんでした。
寒川氏 いや、議会は大事ですね。実は横須賀市は1990年代後半から電子決裁基盤をつくったり、公文書管理システムを導入したりして、一時期は「電子自治体」として進んでいたのですが、2005年ごろに議会から「そんなシステムにお金を投資するのは時期尚早だ」と厳しく批判されて失速していったという経緯がありました。私はその経緯を見ていたので、絶対に議会を失望させてはいけないという思いがありました。
だから議会に対しては、何のためにこの改革をやるのか、投資効果はどうなのかということもきちんと示して、納得いただいた結果、議会が本当に我々の味方になってくれました。特に窓口改革をやった際には、議会が我々を信じてくれたと実感しました。議会が「こういうことを期待していたのだ」と後押ししてくれて、そこで一気に波に乗れました。
小田 自治体のDX関連施策を進める際、「議会への説明はどうしましょうか」と職員に問うと「議会は分からないから説明は必要ないですよ」と言われることが殆どです。特に地方に行くと、高齢の議員が多いせいでしょうか。議員から「DXなんて分からない」「カタカナを使うな」などと言われて「じゃあ分からないなら説明しない」となってしまっています。そこは乗り越えなければいけない部分の一つですね。
寒川氏 予算を決めるのは議会なので、議会の信頼がなければ絶対に無理です。議会が予算に反対したら、何もできないじゃないですか。やはりきちんと議会に説明しないといけません。
組織的な壁と課長級の抵抗
小田 市長、副市長などの自治体幹部、それから議会が重要であると。ちなみに、部長クラスはどうだったのですか?
寒川氏 当初、部長クラスはなんとなく「やらなければいけない」という思いがあって、反対する人はいませんでした。ただ、課長級は全然違いましたね。「なぜ我々があなたの言うことを聞いてやらなければいけないのか」という反応でした。DXの必要性が浸透していなかったのです。話をする中で、前例踏襲で変えたくないという姿勢が見られました。
小田 主に課長級が抵抗勢力だったのですか?
寒川氏 課長級は自分の課題を優先したいという考えと、市役所の縦割り組織の問題がありました。「我々の領域に介入するな」という姿勢で、「なぜあなたの指示に従う必要があるのか」と拒否していたのです。これは典型的な地方自治体の縦割り組織主義です。
また、50代付近の主任・係長級が最も抵抗が強く、「なぜ私のやり方ではいけないのか」と長年の習慣で職人のように凝り固まっていて、そういった人たちの意識を変えるのは本当に困難でした。
危機感の共有と次世代の管理職の育成
小田 一般職員に危機感はあるのでしょうか?
寒川氏 若い職員の皆さんには本当に助けられています。神奈川県の中でも横須賀市は人口減少や高齢化が特に深刻な状況です。この危機感は行政の中で頭では共有されているはずなのですが、それが具体的な施策や行動に結び付いていない現状があります。
最近、新任課長研修の場で「課長になって1カ月がたちますが、皆さんは横須賀市が危機的状況にあることを理解していますか?」と質問したところ、手を挙げたのは1人だけでした。「1カ月何をしていたのか」と思い、かなり厳しく講義を進めました。
役所の最大の問題はセクショナリズムが強いことです。例えば「市の予算は幾らですか?」と聞くと「予算は財政の担当だから」と答え、「採用人数はどうなっていますか?」と聞くと「それは人事がやることだから」と言います。自分の小さな課題しか見ないというのが役人の最大の問題です。
全体を見て「都市経営とは何か」という視点がないことが、市の管理職の最大の問題だと思っています。限られた税財源をいかに効率よく分配して市政を回していくかを考えなければいけないのに、セクショナリズムで考えるからそういう視点がないのです。そこが一番の課題だと思います。
小田 これは多くの自治体に共通する問題です。これまでのご経験の中で、どうしたらこの問題を解決できると思いますか?
寒川氏 資料は課長級の職員とも共有しているのです。情報は共有されているので、資料を見れば危機感が分かるはずなのに、なぜそれを真剣に受け止めないのかという疑問がありました。「人口はこれだけ減っています」「基金(貯金)が何年後になくなります」ということも伝えられていて、それは非常に深刻な問題のはずです。
「業務がうまくいっていない」という話も共有されている。「では我々の組織はもっとコンパクトに効率化しなければ今後も維持することは無理ではないか」と普通は感じるはずなのですが、人ごとというか自分のこととして捉えない人が多いですね。その理由は、「自分の仕事ではない」と思っている人が多いことです。結局、組織が潰れる可能性がなく絶対的な危機感がないから、そういう姿勢になってしまうのだと思います。
今は状況が変わってきています。副市長自身も強い危機感を持っており、市長がなぜこのような思いで都市経営・市政運営をしているのかということを、部長級、課長級職員を含めて講義を行っています。副市長自ら横須賀市の現状を説明し、市長が目指している市政運営はこのような課題があるからこうした取り組みを行っているのだということを、全ての部局長、課長クラスまで伝えています。
副市長は、一般職員全員にも伝えたいと言っていますが、時間の制約もあってなかなか難しい状況です。
人材育成と採用方針の特徴
小田 組織風土改革や全庁的なマインド改革をやりつつも、デジタルの専門技術的なこともやり、外部との連携など、さまざまなことを担当しなければならない組織ですね。庁内の人材はある程度異動すると思いますが、どのように育て、あるいは人材を回していますか?
寒川氏 私は基本的に、デジタルが得意な人よりも改革マインドを持っている人材を重視しています。そのため、パソコンの達人というだけでは採用しません。人事部門にも、現在の業務プロセスに疑問を抱ける人材を求めていると伝えています。実際、技術系の部署から異動した人でもパソコンが苦手だったが、今ではRPA導入やkintone導入を自主的に進めるようになりました。
私はよく「新しい部署に行ったら法律と条例を覚えるのと同じで、デジタルも学べる」と説明しています。本当に複雑なデジタル技術は委託すればいいのです。ただし、我々が適切な課題要件を満たして発注しなければ、質の低いものができてしまうので、その点は注意が必要です。
小田 チーム内のパソコンを使える技術者も改革意識を持っている人ばかりなのですか?
寒川氏 必要な知識は内部で育成できますし、それで特に問題はありません。私はデジタル技術よりも改革意識を持った人材が重要だと考えています。
横須賀市のデジタル変革は単なる技術導入ではなく、組織文化の根本的な変革を目指すものです。上地市長のリーダーシップと「市民に寄り添う」という明確な理念の下、さまざまな組織的障壁を乗り越えながら、着実に進展しています。寒川氏が強調するのは、技術自体よりも「改革マインド」の重要性です。次回は、具体的な成果や課題解決の実践例についてさらに詳しく伺います。
(第3回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年6月2日号
【プロフィール】

寒川 孝之(さむかわ・たかゆき)
窓口・福祉部門を経て2001年に情報政策課(情報システム部門)へ配属。ICカードの実証実験「IT装備都市研究事業」を担当。05年に横須賀市コールセンターを開設後、大規模土地利用によるまちづくり事業に従事。
14年から複数回実施された臨時福祉給付金支給業務を統括、17年からオリンピック担当となり、イスラエル柔道チームの事前キャンプ誘致を実現。20年4月、横須賀市経営企画部デジタル・ガバメント推進室長に就任、2024年から現職。