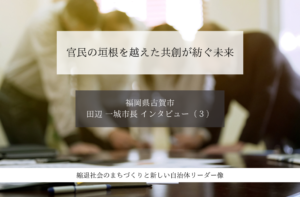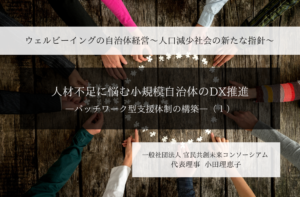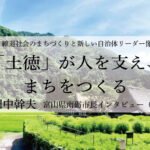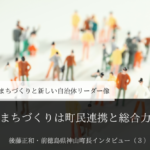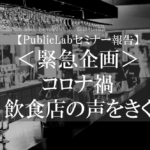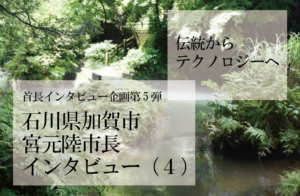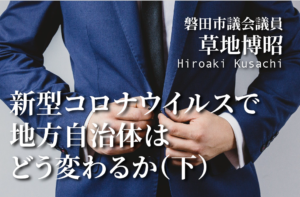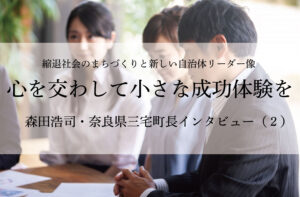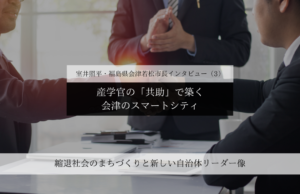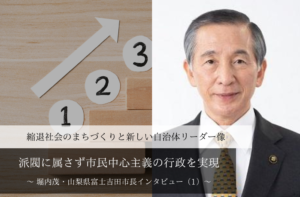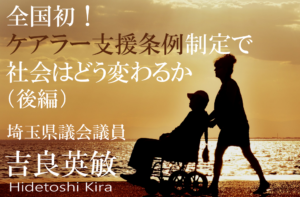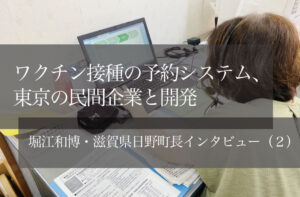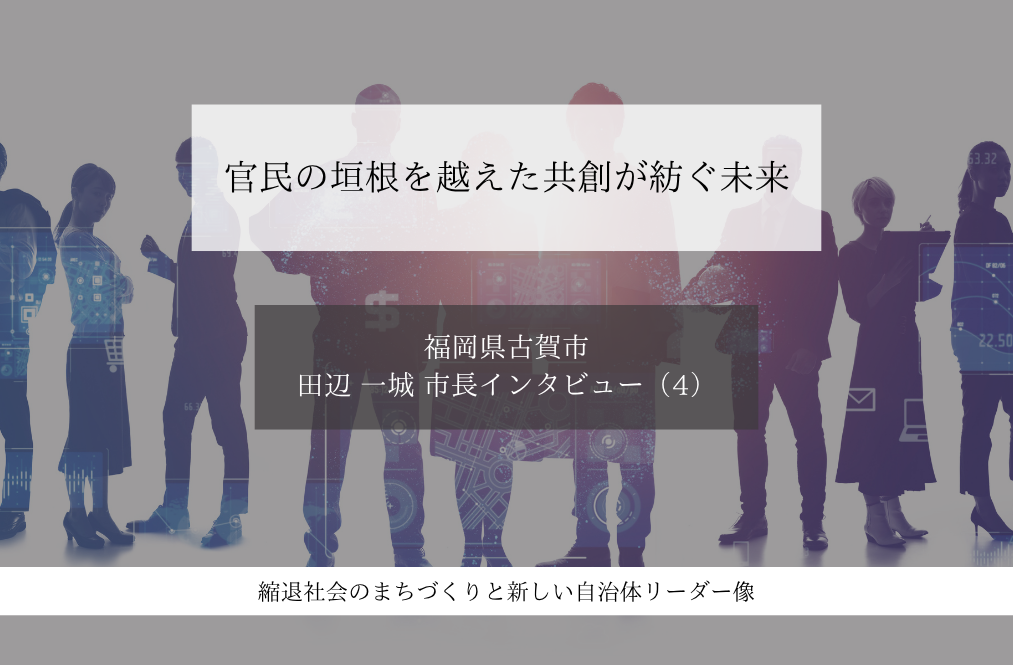
福岡県古賀市長 田辺一城
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/10/29 「走りながら考える」都市経営~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(1)~
2025/10/30 「走りながら考える」都市経営~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(2)~
2025/11/4 官民の垣根を越えた共創が紡ぐ未来~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(3)~
2025/11/6 官民の垣根を越えた共創が紡ぐ未来~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(4)~
課題設定すら民間に委ねる「実証実験事業」の大胆さ
小田 古賀市では「実証実験事業」という非常にユニークな制度を導入されていますね。
田辺市長 2023年度から実施している制度で、一般的な行政の委託事業とは発想が全く逆の、非常にユニークな取り組みだと自負しています。
小田 と言いますと?
田辺市長 通常、行政が事業を発注する際は「こういう課題があるので、こういう解決策を実施してください」と仕様書で細かく要件を決めますよね。しかし、この制度では、市は具体的な課題すら提示しません。
民間事業者に対して「あなたは、今の古賀市にどんな社会課題があると考えますか? そして、それをあなたの技術やノウハウでどう解決しますか?」と、課題設定から解決策までを丸ごと提案してもらうのです。
小田 それは非常に大胆ですね。行政が「自分たちだけでは課題に気付けていないかもしれない」という前提に立っている。
田辺市長 まさにその通りです。行政単独では実現困難な、あるいは思いもよらないような解決策が、民間の自由な発想から生まれることを期待しています。既にこの事業から、本採用に至った素晴らしいサービスも生まれています。
行政がすべてをコントロールしようとするのではなく、多様な主体が持つ知見と能力を最大限に引き出す。これもまた、古賀市が目指す「共創」の形です。
「シェア」の発想が生んだ学校プール民間委託の舞台裏
小田 教育分野でも興味深い「共創」の事例がありますね。学校プールの民間委託について教えてください。
田辺市長 これは実は、私の就任以前から教育委員会で必要性が議論されていた案件でした。教育長が「シェアリングエコノミー」という言葉は使わないまでも、その発想で一部実証も行われていたのです。
私がその話を聞いて「これはいいのではないか」と感じ、特に財政的な側面を考慮して最終的に関与し、2年前から市内の全11校で本格実施することにしました。
小田 どのような効果が生まれていますか?
田辺市長 老朽化する学校プールを維持・管理していくのは、財政的にも大きな負担です。民間のスイミングスクールに委託することで、年間約3000万円の財政効果が生まれるだけでなく、子どもたちは専門インストラクターの指導で泳ぎが上達し、教員の負担も軽減される。保護者からの評価も非常に高い。
既存の公共資源に固執せず、民間の力を借りて再配分することで、より質の高いサービスを提供する。これも「場のシェア」という発想に基づいた「共創」の好例だと思います。
発想の源泉は人との繋がり
小田 市長の新しい発想の源泉は、どこにあるのでしょうか。
田辺市長 私の発想のほとんどは、人とのコミュニケーションから生まれています。「とにかく人と会い、知り合い、語らう機会」を何よりも重視しています。これも新聞記者時代の基本動作ですが、多様な分野の人々と繋がることで対話と交流が生まれ、そこから新たな情報やアイデアが流れ込んでくる。
理念や方向性を示すことと、こうしたネットワークを構築することが、私の仕事の大半を占めていると言っても過言ではありません。
小田 実際に、市長の元には無数のメッセージが届くと聞きました。
田辺市長 はい。そして、そのほとんどを秘書任せにせず、自分で直接やりとりしています。多くの首長は秘書に任せるのかもしれませんが、それではどうしてもスピードが削がれてしまう。直接対話することで、スピードを維持し、相手との深い信頼関係を築くことができるんです。
これも「共創」の基盤となる考え方です。多様な人々との直接的なコミュニケーションがあってこそ、真の協働が生まれるのだと信じています。
宇宙への挑戦──「食のまち」が描く壮大な未来図
小田 古賀市の挑戦の未来像についてお聞かせください。非常に壮大なビジョンをお持ちだと伺いました。
田辺市長 はい(笑)。これまで話してきたDX、シェアリングエコノミー、そして公民連携による「共創」──これらすべての延長線上に、私たちは「自治体から、宇宙のライフスタイルをつくる」という壮大なビジョンを掲げています。
小田 宇宙ですか!
田辺市長 突拍子もなく聞こえるかもしれませんが、古賀市は「食のまち」であり、食品加工をはじめとする工業製品の出荷額も高いという強みがあります。この強みを活かせば、まずは「宇宙食」の分野で貢献できるのではないか、と本気で考えています。
地域の課題解決から始まった「共創」の取り組みが、やがては人類全体の課題である宇宙開発にまで繋がっていく。これこそが、多様な主体との協働によって無限の可能性を追求する「共創」の究極の形かもしれません。DXも、共創も、すべては未来を創るための挑戦なのです
全国の自治体職員へのメッセージ
小田 最後に、この記事を読んでいる全国の自治体職員の皆さんへメッセージをお願いします。
田辺市長 私から偉そうなことは何も言えません。ただ、皆さんに伝えたいのは、ぜひそれぞれの首長に積極的に提案し、コミュニケーションを取ってほしい、ということです。
最終的な決断と責任は首長が負いますが、現場で改善できる業務は無数にあるはずです。「走りながら考える」という姿勢で、変化の速い時代に対応し、他の自治体とも学び合いながら、社会全体を良くしていく。
「共創」は決して特別なことではありません。多様な人々の知恵と情熱を信じ、繋がり、協働する。それこそが、これからの公務員が担うべき、大きく、やりがいのある役割だと私は信じています。
【編集後記】
休業した温泉旅館がワーケーション拠点に生まれ変わり、半世紀の懸案だった駅周辺開発が動きだし、行政が課題設定すら民間に委ねる実証実験事業が花開く。古賀市で起きているこれらの変革は、すべて「多様な主体への深い信頼」という一点から始まっていました。
「政治家は住民の道具にすぎない」と語る田辺市長の言葉は、謙遜ではなく確信に満ちています。道具は使われてこそ価値を持つ。だからこそ現場を駆け回り、対話を重ね、「共創」という名の信頼関係を紡ぎ続ける。トップ自らが汗をかき、言葉を尽くし、相手の目を見て語り掛ける。その熱量こそが、不可能を可能に変える原動力となるのでしょう。
人口減少という現実を前に、多くの自治体が縮小均衡を余儀なくされています。しかし古賀市の歩みは、リーダーの覚悟と市民・民間への信頼があれば、地域の未来は無限に切り拓けることを証明しています。「共創」は特別な技術ではありません。相手を信じ、対話し、一緒に汗をかく──そんな当たり前の積み重ねが、やがて大きな変革の波となって地域を変えていくのでしょう。
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年9月29日号
【プロフィール】
 田辺 一城(たなべ・かずき)
田辺 一城(たなべ・かずき)
1980年生まれ。慶大法卒。2003年毎日新聞社に入り、記者として活動。
11年福岡県議選に初当選(15年再選)。18年同県古賀市長選に初当選し、現在2期目。