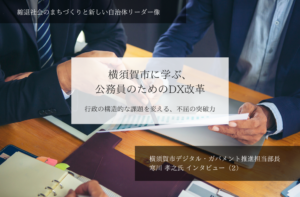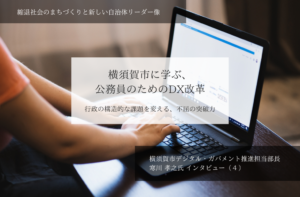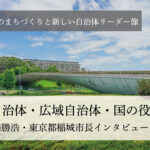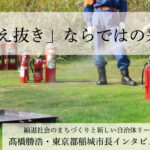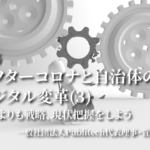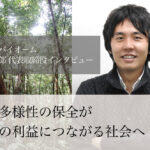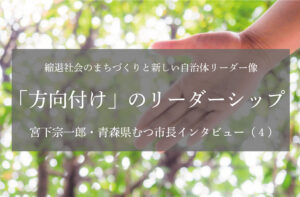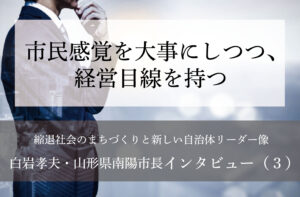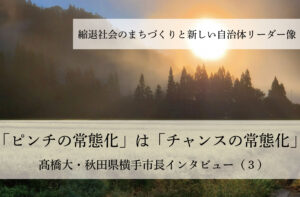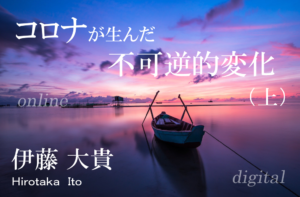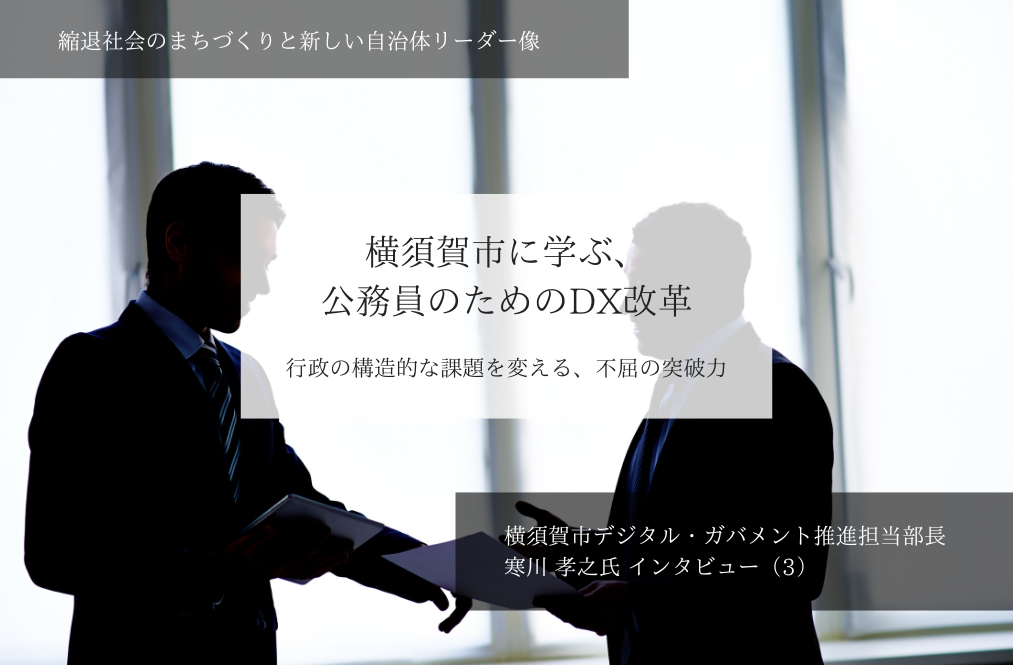
神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長 寒川孝之
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/07/09 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(1)~
2025/07/10 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(2)~
2025/07/15 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(3)~
2025/07/17 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(4)~
これまでのインタビューでは、神奈川県横須賀市のデジタル変革を推進する上地克明市長のリーダーシップと、組織変革の過程における課題について伺いました。後編では、具体的な取り組みの実践例や成果、そして改革の本質について、引き続きデジタル・ガバメント推進の実務を担当する寒川孝之氏にお話を伺います。(聞き手=一般社団法人官民共創未来コンソーシアム代表理事・小田理恵子)
外部人材の活用とその選定基準
小田 前編では庁内の人材育成について伺いましたが、外部人材の活用ではいかがでしょうか?
寒川氏 AI(人工知能)の分野は日進月歩で進化するため、我々が追い付くのは困難と判断しました。自治体初のAI全庁導入を発表した2023年4月、横須賀出身のAI専門家・深津貴之さんが「おぉ、我が地元‼ レクチャーとかノウハウとか、無限に提供したい」とツイートしてくださいました。この縁でお会いする機会を得て、アドバイザー就任をお願いしたところ、快諾いただきました。
また、ICT(情報通信技術)戦略専門官を外部から招聘し、現在は構造改革担当部長として活躍しています。大局的視野を持つ外部人材の登用は非常に有効だと実感しています。
その効果は予算獲得の場面でも表れました。21年の予算要求では、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進のために詳細な内訳なしで1億円と記載したため財務部が激怒し、急遽、両副市長同席の予算要求に関する会議が開かれました。その場で外部招聘したICT戦略専門官が「財務部は今まで優先的にICT機器を活用しているにもかかわらず投資効果を示したことがあるのですか?」と発言してくれたおかげで、なんとか予算を獲得できたのです。
小田 1億円とだけ書いて提出したのは意図的だったのですよね。
寒川氏 そうです。DXは正解があるものではないので、予算要求の仕方も変えていいと思ったのです。結果的に8000万円に減額されましたが、必要に応じて予算を適正に執行しています。
小田 次回もひと固まりで予算要求する方針ですか?
寒川氏 はい。そのやり方で予算がつくようになりました。財務部長も「投資する」と説明してくれるようになりました。 我々の(主張する)削減効果を信じてくれて、大激論の末、応援してくれる方向に変わったのです。
小田 みんなでけんかした後、夕日に向かって走るような感じですね(笑)。
寒川氏 そうですね。その割には2000万円削られましたけど(笑)。
財務部長も、最後は必要な部分は投資するという考え方で、我々を信じてくれたので、私も予算を使うときには「こういった形で効果が出るからやります」という説明をして、無駄に使わないようにしています。そういったところも信用してもらえた理由だと思います。今はもう先が見えない状況なので、やってみないと分からないことがあります。積み上げ式の予算計画は難しいのです。
多くの自治体では「今予算がないから来年度に」となり、結果的にDXによる行政改革が遅れることが多いのですが、横須賀市はすぐに新しい技術を取り入れ改革を進めることができています。
小田 だから横須賀市は生成AIも早い段階で取り入れることができたのですね。
寒川氏 はい。もちろん投資効果のないものは実施しませんが、柔軟な対応ができています。時には予算を数千万円残してしまうこともありますが、それはきちんと不用額としてお金を返しています。決算については議会に対してとても丁寧に説明していますよ。
小田 関連する質問ですが、重要業績評価指標(KPI)についてはどうされていますか? 自治体はよくKPIを設定したがりますが、投資対効果はどのように測定されていますか?
寒川氏 これまではイニシャルコストを積み上げて、職員の時間外勤務がどれだけ減ったとか、用紙の使用量がどれだけ減ったかといった金額を全部積み上げて、いつ回収できたかを議会に報告しています。削減効果や回収期間などですね。これも議会から「散々DXと言っているけれど、ちゃんと効果は出ているのか」と当然質問されたので、24年3月の議会に報告しました。
小田 施策と結果がすぐに結び付かないものや、うまくいかないケースについてはどのように対応されていますか?
寒川氏 基本的にはデータ分析に基づいて「これによってどの程度業務が削減されるか」という観点から説明しています。しかし、現場が途中で取り組みを中止してしまい、期待された効果が得られないケースもあります。
具体例として、生活保護業務にRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とAI-OCR(光学式文字読み取り装置)を導入して自動化システムを構築しましたが、会計年度任用職員の仕事がなくなるという理由によって中止されたことがありました。そのような場合は、RPAのライセンスや機器をすべて引き揚げて停止することもあります。
小田 そういったことも起こり得ますね。トライ・アンド・エラーを繰り返すのは失敗ではなく、改革の過程では自然なこととも言えるでしょう。
業務プロセスの可視化と改革アプローチ
小田 トッパン・フォームズ社(現TOPPANエッジ社)と共同でBPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)の研修を継続的に実施されていると聞きました。通常、現場の方々は業務フローを書くのが難しいものですが、最初はどのような状況だったのですか?
寒川氏 19年12月にトッパン社さんとデジタル・ガバメント推進に関する包括連携協定を締結し、翌年3月に同社の協力でトライアル研修を実施しました。効果を実感したので、20年度から予算化して継続しています。
この研修では業務フローの作成よりも、業務の関係性や全体の動きを把握することを重視しています。現状を正確に把握した上で、あるべき姿と比較します。すべてを詳細に分析すると時間がかかるため、重要な部分に焦点を当てています。
この取り組みを中止すると組織が弱体化すると考えているので、継続していく予定です。日々の業務に追われる中で、職員は業務の関係性やプロセスの前後関係を見る余裕がないのが現状です。
小田 そうですね。日常業務に追われていますから。
寒川氏 BPM研修はその課題を改善できる良い機会です。最近は「なぜこのようなやり方をしているのか」と疑問を持つ人たちの参加が増えています。既存のやり方に疑問を投げ掛ける人たちが改革を推進しているのが最近の特徴です。
小田 そういう人材が増えれば現場での改革も進みますね。
寒川氏 そうなのです。それを狙っています。
小田 この取り組みを始めてから、どのくらいの期間で現場が変わってきたという感覚をお持ちですか?
寒川氏 私が担当した20年の初年度は、総務部と土木部(現在の建設部)で始めました。建設部では成功したのですが、総務部ではうまくいきませんでした。決裁・公文書管理システムが1990年代後半から稼働していたにもかかわらず、今でも紙決裁を残していたことについて、総務部に「考え直すべきだ」と提案したのですが 「条例・規則を守ることの何が悪いのか」と言われて、結局改革は進みませんでした。
私は諦め切れなかったので、当時の総務部長に頼んで、若手職員と関係者を集めた会議に出席させてもらい、DXについて説明する機会を設けました。そして3年間、毎週会議をやりました。
小田 総務部に対してですか? 3年も? ずいぶん長くかかりましたね。
寒川氏 はい。DXの必要性や本質について説明し続けました。 そして3年経って、ようやく公文書管理規則と管理規程を見直し、紙決裁をやめることができました。今では電子決裁率は98%です。このような変更に3年もかかるなんて信じられないですよね。私は1カ月で変わると思っていたのに。市役所の組織文化を変えるのは本当に大変です。
小田 寒川さんの登壇動画の中で、こうした取り組みによって各現場に少しずつ改革マインドが醸成されていって、特に消防局が積極的だったというお話を拝見しました。これはなぜでしょうか。
寒川氏 消防は「命を守る」という使命に強く燃えているのです。横須賀は中核市規模ながら出張所が多く、消防の分署も多いです。彼らは以前、月1回本庁に集まって会議を行っていましたが、「本庁に来ている間に事故が起きたら市民を守れない」という危機感を持っていました。そのためWeb会議環境の早期構築を望んだのです。「市民の命を守る」という使命感が彼らは強いのです。
彼らの協力には本当に感謝しています。VR(仮想現実)を活用した避難訓練の実施や、救急現場のカメラ映像を病院と共有する総務省の実証実験など、先進的でさまざまな取り組みを前向きに進めてくれています。
小田 胸の熱くなる話です。そして、やはりマインドありきなのですね。
寒川氏 根本的には、デジタル化自体が目的ではなく、いかに効率的にするかが最も重要だと考えています。技術はそれに従うものです。つまり、変革(トランスフォーメーション)が最も大切なのです。
小田 そうですね。必ずしも100%紙をデジタル化する必要はなく、全員がパソコンでメモを取らなければならないというわけでもありません。
寒川氏 今はそこが焦点ではないのです。いかに簡単にやるかが大事で、でも紙も結局は行政経費ですから。私は財務部長によく「お金がないと言いながら、なぜ議会の時に分厚い辞書のような資料を印刷してくるのか」と指摘します。役人は「自分のお金ではないから」と無駄が多いのです。「予算がない」と言うなら徹底的に無駄を省いてスリム化すべきですが、役所ではそういった意識が欠けています。
(第4回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年6月9日号
【プロフィール】

寒川 孝之(さむかわ・たかゆき)
窓口・福祉部門を経て2001年に情報政策課(情報システム部門)へ配属。ICカードの実証実験「IT装備都市研究事業」を担当。05年に横須賀市コールセンターを開設後、大規模土地利用によるまちづくり事業に従事。
14年から複数回実施された臨時福祉給付金支給業務を統括、17年からオリンピック担当となり、イスラエル柔道チームの事前キャンプ誘致を実現。20年4月、横須賀市経営企画部デジタル・ガバメント推進室長に就任、2024年から現職。