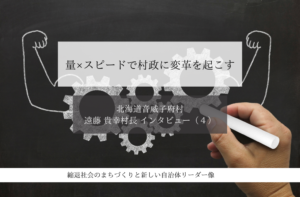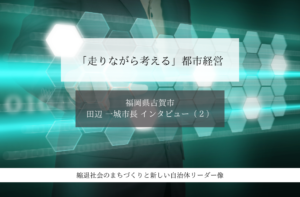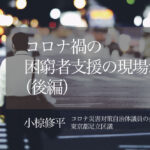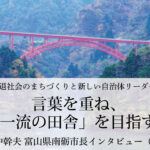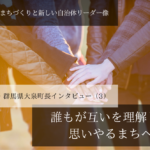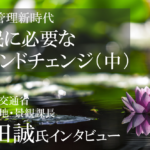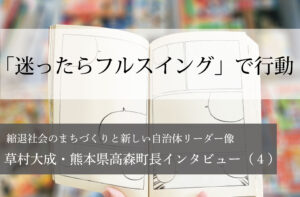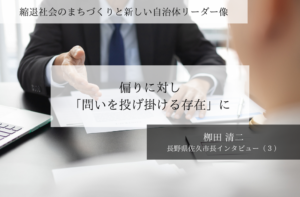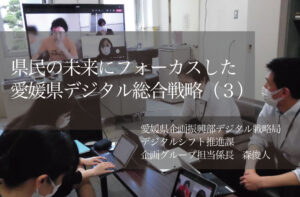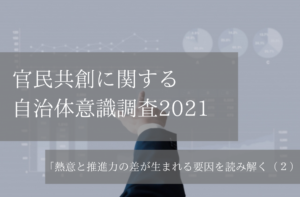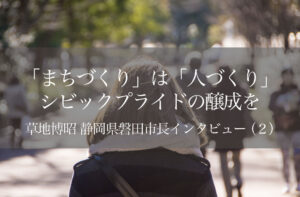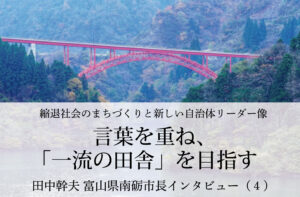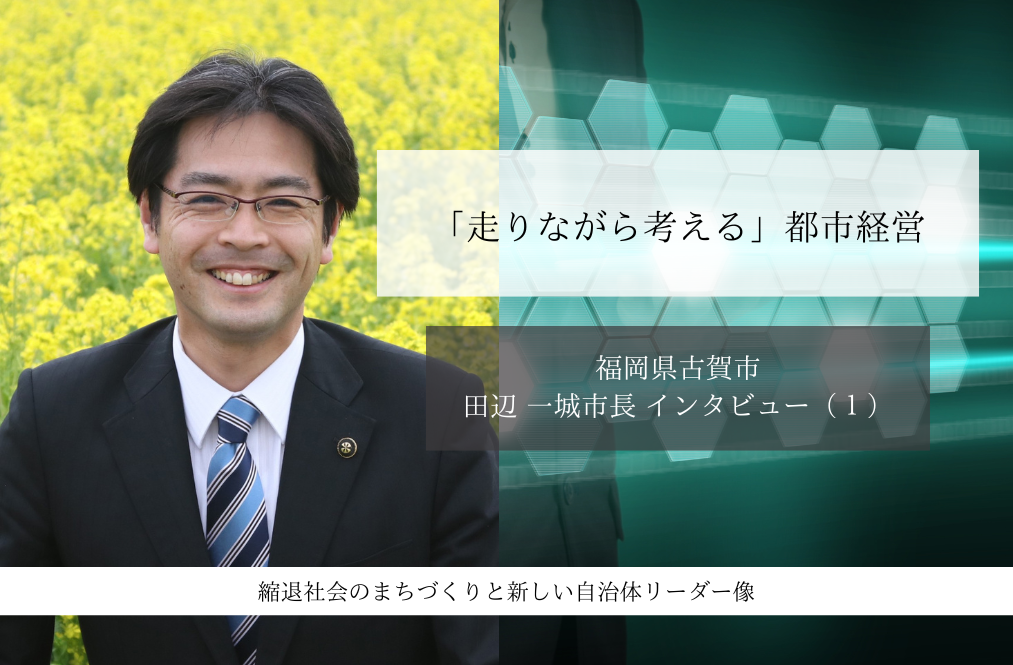
福岡県古賀市長 田辺一城
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/10/29 「走りながら考える」都市経営~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(1)~
2025/10/30 「走りながら考える」都市経営~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(2)~
2025/11/4 官民の垣根を越えた共創が紡ぐ未来~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(3)~
2025/11/6 官民の垣根を越えた共創が紡ぐ未来~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(4)~
福岡県のコンパクトシティ、古賀市。福岡市と北九州市の中間に位置し、交通の利便性にも恵まれたこのまちが今、人口減少社会における持続可能な都市経営のモデルとして、全国から熱い視線を集めています。
「シェアリングエコノミー」「DX(デジタルトランスフォーメーション」「公民連携」の三つを柱に、次々と革新的な政策を打ち出す田辺一城市長。その改革のスピードと熱量はどこから生まれるのでしょうか。
今回は、田辺市長へのインタビューを通じ、その核心に迫ります。前編では、コロナ禍という未曽有の危機に試されたリーダーシップの源泉、そして「走りながら考える」という独特の経営哲学、さらには行政内部から変革のうねりを起こした組織論に焦点を当てます。なぜ古賀市は変わらなければならなかったのか。その根源的な動機と覚悟を、市長自身の言葉で紐解いていきます。(聞き手=一般社団法人官民共創未来コンソーシアム代表理事・小田理恵子)
「走りながら考える」スピード感の源泉と〝有事〟の想像力
小田 古賀市の政策実行のスピード感には、いつも驚かされます。田辺市長は現在2期7年目ですが、市長就任以来、何か明確なロードマップを描いて進めてこられたのでしょうか?
田辺市長 いいえ、ロードマップは全く描いていません。古賀市の自治体経営がスピード感を持っていると言われるとすれば、その最大のポイントは「走りながら考える」、そして「決める」ということに尽きると思います。
もちろん、中長期的な計画を否定するわけではありません。それは非常に大事です。しかし、私に付託された時間は限られています。時代の変化がこれだけ速い現代において、計画を緻密に練り上げている間に状況は変わってしまう。だからこそ、まず動く。この姿勢が一貫しているからだと思います。
その根底には、新聞記者時代に培った「現場主義」と「対話と交流」の精神があります。日々多くの人と繋がり、対話から生まれる「一次情報」を重視し、自らも毎日歩きながら市政を熟考しています。

インタビューに答える田辺市長(出典:官民共創未来コンソーシアム)
小田 「走りながら考える」という哲学が、最も試されたのはどのような場面でしたか?
田辺市長 やはり、コロナ禍の初期対応でしょうね。平時ではない「有事」において、現場で何が起きているかを詳細に調査している時間はありません。そこで重要だったのが「想像性」でした。これはクリエイティブという意味ではなく、これまでの経験に基づいて、この状況で社会のどの部分に、どのような歪みが生まれているかを「想い描く」力です。
小田 具体的な事例をお聞かせいただけますか?
田辺市長 例えば、ひとり親家庭への5万円の現金給付は、全国的に見てもかなり早い段階で実施しました。これは私が新聞記者時代から、日本のひとり親家庭の貧困率が極めて高いという現実を知っていたからです。コロナ禍で経済活動が止まった時、不安定な職業に就かれている方が多いひとり親家庭が、真っ先に深刻な打撃を受けるだろうと想像しました。だからこそ、プッシュ型での早期の現金給付が必要だと即座に判断したのです。
もう一つ、印象に残っているのが医療的ケア児への対応です。お子さんやそのご家族は、日常的にアルコール消毒が欠かせません。しかし、コロナ禍であっという間に市中からアルコール消毒液が消えました。この時も、現場から悲鳴が上がるのを待つのではなく、「市の備蓄を直ちにプッシュ型で送れ」と指示しました。実際に約20世帯にお届けしましたが、これも詳細な実態調査を経たわけではありません。先手を打った結果です。後日、SNSで当事者の方から感謝の声が直接届き、間違っていなかったと確信しました。
小田 過去の経験や知識の蓄積が、有事における迅速な意思決定に繋がっているのですね。
田辺市長 そうです。首長の仕事は、理念をしっかりと掲げ、職員を鼓舞し、そして決めるべきときに決めることで全責任を負うこと。特に有事においては、この「決断」のスピードが市民の命や暮らしを左右すると考えています。
人口減少社会の処方箋─三つの柱が生まれた背景
小田 市長は「シェアリングエコノミー」「DX」「公民連携」を古賀市の三つの柱として掲げられています。これらの構想はいつ頃から温められていたのでしょうか?
田辺市長 実は、就任当初から明確な三本柱があったわけではありません。「走りながら考える」中で、人口減少社会という現実と向き合って、必然的に辿り着いた答えがこの三つだったのです。
特にシェアリングエコノミーは、人口減少が進む中で地域のリソースが不足してきている現実への処方箋として位置付けています。限りある資源を「共同化」や「共有化」することで最大限に活用し、持続可能性を高める。人、モノ、コト、スキルといった多様なものを共有することで、合理化を図りながら可能性を広げるという考え方です。
そして、DXについては、単なるデジタル化にとどまらず、その先の「変革」を追求するための重要な手段と捉えています。「D」ではなく「X」こそが重要。デジタル技術は、組織や社会の在り方を変革し、より良い社会や働き方を生み出すための手段なのです。
小田 その理念を、まず行政内部から実践されているのが印象的です。
田辺市長 その通りです。シェアリングエコノミーを推進する古賀市にとって、まず行政内部から「シェア」を実践することが重要だと考えました。また、シェアリングは多様な生き方を保障し、市役所内外の働き方改革を推進するための重要な要素でもあります。働く「場」を変えることで、新たな発想や仕事の仕方を生み出すことができると信じています。
変革は庁内から職員の意識を変えた「シェア」の実践
小田 市長室をご自身が不在時にシェアするという取り組みは、非常に象徴的です。
田辺市長 あれは、私がSNSで「市長室もシェアできたらいいなー、と密かに思っています。私が出張で不在はよくあるので。スペースを有効に活用できたらいいですね。」とつぶやいたのがきっかけで、職員が「ではシェアしましょう」と応じてくれたんです。だったら、本当にやろう、と即採用しました。働く「場」が変われば、仕事の仕方も、発想も変わる。まずは私自身が、そして行政が内側から変わる姿を見せることが重要だと考えました。

不在時にシェアする市長室(出典:田辺一城note)
小田 市長自らが「実践」することで、職員に具体的な変化のメッセージを送ったわけですね。フリーアドレス制の導入もその一環でしょうか。
田辺市長 その通りです。職員の発案を受けて、まずは上下水道課で先行実施し、今年度からさらに四つのセクションに広げます。「固定席は本当に必要なのか?」という問い掛けから、職員の働き方に対する意識は確実に変化しました。
小田 その意識変化が最も顕著に表れたのが、男性職員の育児休業取得率だと伺いました。
田辺市長 はい。私が就任した2018年当時は10%前後でしたが、22年度には100%を達成しました。最近では半年間の育休を取得する職員も出てきています。これは単なる制度利用促進にとどまらず、「誰かが休んでも組織は回る」というメッセージを共有し、多様な働き方を許容する組織文化が根付いた証拠です。
ジェンダー平等は当然のこととして推進してきましたが、結果として、職員一人ひとりが自律的に動き、互いに支え合う柔軟な組織運営へと繋がりました。これは、古賀市が推進する「シェアリング」の精神が、行政内部に浸透した結果だと捉えています。
(第2回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年9月22日号
【プロフィール】
 田辺 一城(たなべ・かずき)
田辺 一城(たなべ・かずき)
1980年生まれ。慶大法卒。2003年毎日新聞社に入り、記者として活動。
11年福岡県議選に初当選(15年再選)。18年同県古賀市長選に初当選し、現在2期目。