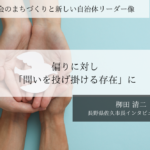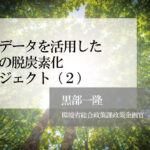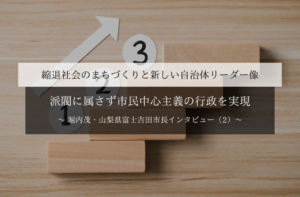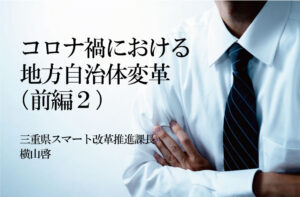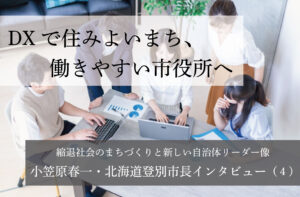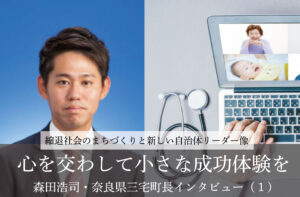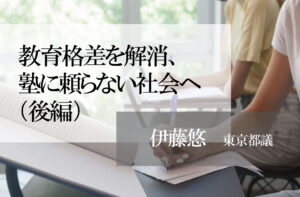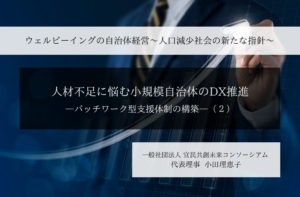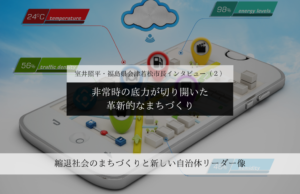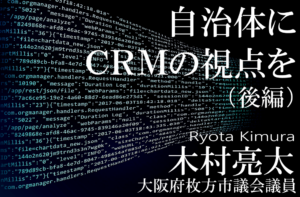北海道名寄市長 加藤剛士
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/08/06 「聞く力」とまちづくりの原点~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(1)~
2025/08/07 「聞く力」とまちづくりの原点~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(2)~
2025/08/12 「保守と斬新」の両輪で拓く名寄の未来~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(3)~
2025/08/14 「保守と斬新」の両輪で拓く名寄の未来~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(4)~
前編では、北海道名寄市の加藤剛士市長の「聞く力」を軸としたリーダーシップの原点、市の歴史的ルーツや道北の要衝としての役割、そして開かれた対話の姿勢に光を当てました。後編では、その「聞く力」から生まれる独自のマネジメント術、市長の哲学である「保守と斬新」の融合、人口減少という大きな課題への具体的な挑戦、そして名寄市の未来への熱い想いに、さらに深く迫ります。(聞き手=一般社団法人官民共創未来コンソーシアム代表理事・小田理恵子)

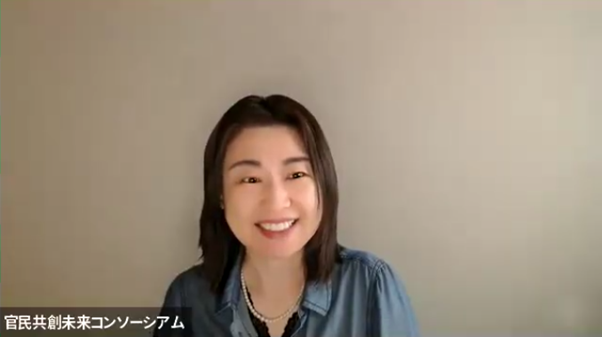
加藤市長(上)へのインタビューはオンラインで行われた(出典:官民共創未来コンソーシアム)
「市長が一番暇でいい」任せて育てるマネジメント
小田 加藤市長は経営者のご経験もあることから、マネジメントに長けた方である印象があります。市長が実践されているマネジメントや組織運営の哲学についてお聞かせください。
加藤市長 私は基本的にボトムアップで市政を進めていきたいと考えています。その一つの例が、数年前に市の公式サービスとして導入したゴミ分別のLINEBotです。もともとは、職員も参加していた市民団体「なよろシビックテック」の方からの提案だったのですが、「これはいいね!」と市としてすぐに対応し、正式に採用させていただきました。現場の良いアイデアは積極的に採り上げていく、それが基本ですね。
小田 市民や職員からの自発的な提案を積極的に採り入れていらっしゃるのですね。現在、市として力を入れているDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進についても、そうしたボトムアップの姿勢が活かされているのでしょうか。
加藤市長 今、人口が減少する中で、行政も仕事のやり方自体を変えていかなければなりません。そうなるとやはりDXの推進は避けて通れないと思っています。こうした新しい取り組みは、やはりデジタルネイティブ世代である若手職員が中心となって進めるべきだと考えています。名寄市でも2022年度からDX推進計画を策定し、若手職員などによるワーキンググループを設置しました。すぐに大きな変化があるわけではありませんが、彼らから多様なアイデアを上げてもらい、実現可能なものから積極的に採り入れています。仕事の在り方自体を変革すべき今、職員の能動的な活躍には強く期待していますね。
小田 職員の自主性を引き出すために、日頃から心掛けていることがあれば教えてください。特に職員の成長を促すためのお考えをお聞かせください。
加藤市長 私は職員に「役所の常識は世間の非常識」と伝えています。組織内連携も大切ですが、それ以上に外部と積極的につながり、多様な価値観に触れてほしいのです。地域のサークル活動や清掃参加が一例ですね。
そうした地域との直接の関わりは、行政内では見えない市民の真のニーズに気付き、職員の成長を促す貴重な機会となります。職員一人ひとりが主体的に動き、視野を広げ、自律的に仕事に取り組めるようになっていけば、組織全体の力も格段に上がります。そうなれば、私自身は細かな業務に逐一指示を出す必要がなくなり、より長期的な視点に集中できるようになる。そういう意味では、結果として私は役所で「一番暇な人間」でいられるのかもしれませんね。そして、それが組織としての理想の姿の一つだと考えています。
小田 「一番暇な人間」というのは、一般的な市長像からすると意外ですが、これは組織運営の理想を表現されているのでしょうか。優秀な組織のトップは時にそのような表現をしますが、その真意について詳しく聞かせてください。
加藤市長 「一番暇」といっても、もちろん言葉通りの意味合いばかりではありません。各分野の仕事はその担当職員がプロフェッショナルとして最もよく理解しているはずですので、まずは現場の職員が中心に進めるべきだと考えています。そして、上がってくるさまざまな選択肢や提案を私が丁寧に精査し、最終的な判断を下してその結果に責任を負う。それが私の役割だと認識しています。
実は、以前に会社経営に携わった経験も少しばかりあるのですが、その時にも痛感しました。トップが一から十まで細かく指示を出すよりも、働く一人ひとりが能力を最大限に発揮できるような環境を整え、その力を信じて任せることこそが、結果として組織全体の力を何倍にも大きくしていくのだ、と。この考え方は、現在の市政運営の根幹にも通じていると感じています。
小田 つまり「一番暇」というのは、職員への信頼と適切な役割分担が機能している証拠ということですね。市長として適切な判断を下すために、日々どのようなことを意識していらっしゃいますか。
加藤市長 判断のための情報を集めていますね。ですから、日常的に庁内をぶらぶら歩いて、職員と直接言葉を交わし、現場の空気を感じながら情報収集することを心掛けています。
伝統を守る「保守」の姿勢、民主的で「斬新」な手法
小田 加藤市長が市政を運営される上で、その根底にある判断の「軸」や、大切にされている「哲学」についてお聞かせいただけますでしょうか。
加藤市長 私の根っこの考え方は「保守」なんです。この「保守」というのは、歴史の中でつくられた伝統や制度を大切にしつつも、民主的な形で斬新な政策を行うことと定義しています。これまで積み重ねられてきた歴史は土台です。一方で、今の社会は非常に急速に流れているので、それに対するアンテナはしっかり張って、いろいろな方とつながりながら現状のベストを選ぶ必要があると考えています。
小田 伝統を重んじる「保守」の土台があってこそ、新しい「斬新」な取り組みも活きてくるということですね。そのバランスを取る上で、リーダーとしてどのようなことを大切にされていますか。
加藤市長 「自分一人の主観だけでは限界がある」という考えです。リーダーは万能感よりも謙虚さを持つことが大事だと思っています。例えば「こうしたい」という思いが浮かんだときには「そこに私心はないか」と自分自身に問い掛けることを心掛けています。最終的に判断するのは首長である私ですが、その判断を行うには、周囲の情報や関係する方たち、これまで積み重ねてきた歴史など、あらゆる背景に対して謙虚であるべきだと思っています。
それから、未来に対して常に明るく前向きな態度でいることですかね。「最近元気がないね」と言われたときには、自分自身の状態がどうであるか省みるようにしています。
小田 ご自身の首長としての在り方にも気を配っていらっしゃるのですね。職員の方々にもご自身のそうしたお考えを伝えていらっしゃるのでしょうか。
加藤市長 自分の考えを一方的に押し付けるのではなく、まず「私はこう思うけれど、あなたはどう思う?」と、相手の意見を真摯に聞きます。そして、その言葉に期待して耳を傾ける。やはり、ここでも「聞く」姿勢が基本ですね。
(第4回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年7月14日号
【プロフィール】

加藤 剛士(かとう・たけし)
1970年11月18日北海道名寄市生まれ。小樽商科大学卒業後、千代田生命保険(現・ジブラルタ生命保険)に勤務。
その後、父が経営するホテル・飲食店グループ「KTバイオニアグループ」に入社し社長を務める。
名寄青年会議所理事などを歴任。2010年、39歳で名寄市長に初当選し、以降無投票を含め4期連続で市長を務める。
全国青年市長会会長も歴任。現在4期目。