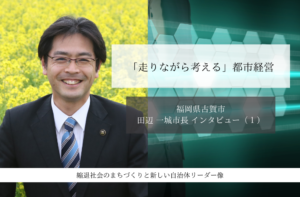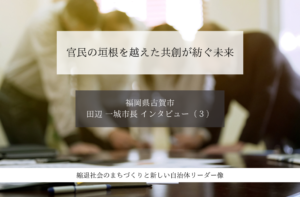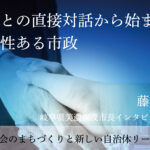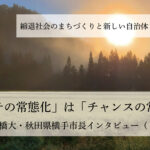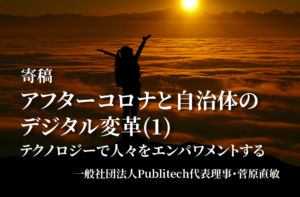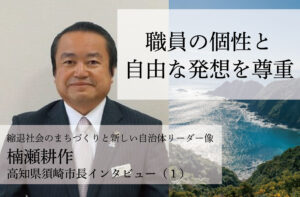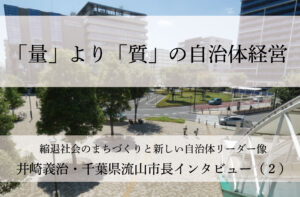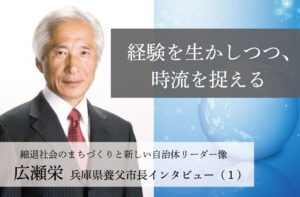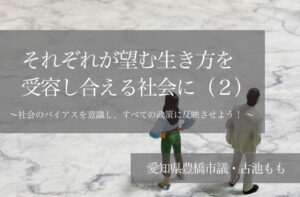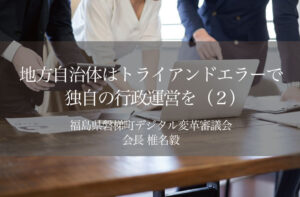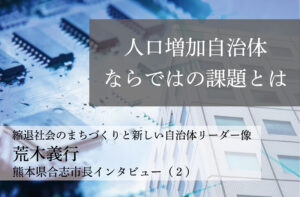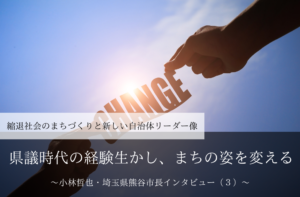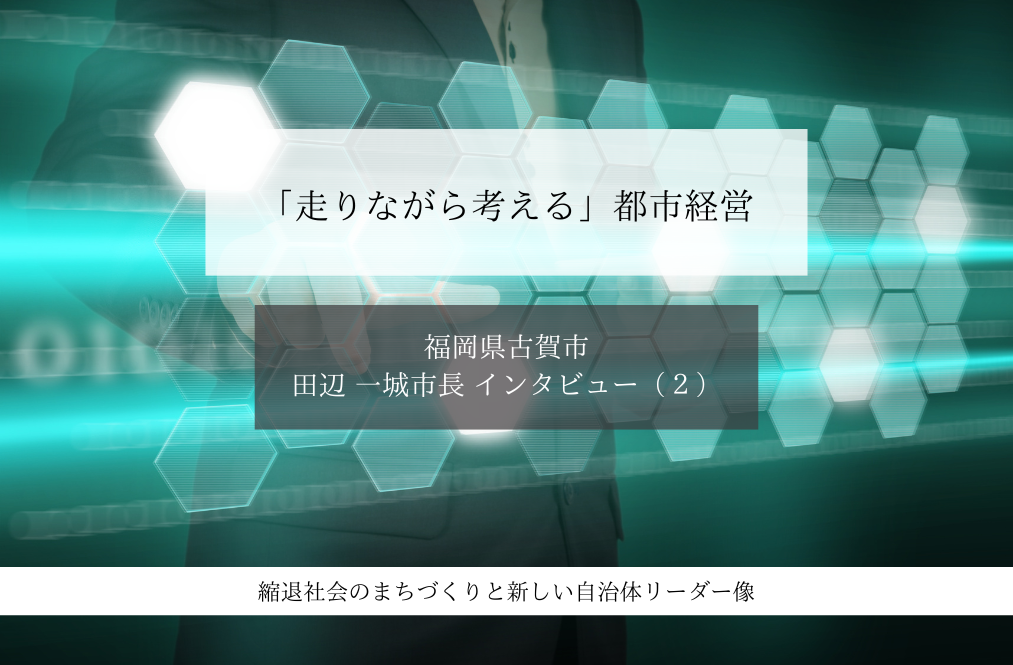
福岡県古賀市長 田辺一城
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/10/29 「走りながら考える」都市経営~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(1)~
2025/10/30 「走りながら考える」都市経営~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(2)~
2025/11/4 官民の垣根を越えた共創が紡ぐ未来~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(3)~
2025/11/6 官民の垣根を越えた共創が紡ぐ未来~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(4)~
DXで実現する「変革」1780時間の業務削減が物語るもの
小田 DXの推進についても、具体的な成果が数多く生まれていますね。
田辺市長 ええ。古賀市では、デジタル推進課が職員からの業務改善相談を受け付けており、24年度には1780時間もの業務時間削減を実現しています。これは、デジタル技術の活用により職員の生産性向上に貢献した証拠です。
具体的には、住民票等のコンビニ交付を積極的に推進し、現在では5割以上の市民がコンビニで取得されています。また、道路台帳や都市計画図といった情報は、24時間いつでもインターネットで閲覧できるGIS(地理情報システム)を導入しました。
さらに、外部の生成AI(人工知能)が持つ偽情報の懸念を回避するため、古賀市が発信している情報をベースとした独自の生成AIも開発しています。業務の効率化と情報の正確性確保を両立させた取り組みです。
小田 庁内DXコンテストという取り組みも興味深いですね。
田辺市長 これは職員からの自発的な提案を促すためのものです。20以上の業務改善事例が生まれ、それらを全職員で共有することで、他の部署での応用も促進されています。重要なのは、厳密な「デジタル計画」を最初から策定していたわけではないということです。
各部署が「できること」を自律的に考えて実行することを奨励し、その結果として多くのデジタル化事例が生まれた後に、それらを体系化する形で計画を策定しました。変化の速い時代に対応するための柔軟なアプローチです。
「やらされる」から「やりたい、やってみよう」の組織風土へ
小田 職員の方々の意識が変わったことで、具体的な業務改善にも繋がっているそうですね。
田辺市長 ええ。職員たちが「クリエイティブに仕事をしていいんだ」と感じてくれるようになったのか、さまざまな提案が自発的に上がってくるようになりました。例えば、「二十歳の集い」でのQRコード受付システムや、保育所の一斉オンライン申し込みといった取り組みは、すべて職員の発案から始まっています。
小田 全国最長とされる、窓口受付時間の90分短縮も、そうした流れの中で実現したのでしょうか。
田辺市長 はい。もちろん、背景にはオンライン申請の拡充やコンビニ交付の普及といったデジタル化の進展があります。しかし、「時間を短縮できるのではないか」というアイデアの起点は現場の職員です。
そして最も重要なのは、短縮によって生み出された時間を、職員が政策立案機能の強化といった、より付加価値の高い業務に振り向けられるようになったことです。効率化が良い循環を生み出しているのです。
小田 トップダウンで明確なビジョンを示しつつも、現場のボトムアップ提案を積極的に吸い上げる。その融合が古賀市の強みだと感じます。職員が主体的に提案しやすい環境は、どのようにしてつくられたのでしょうか?
田辺市長 明示的に「組織風土改革プラン」のようなものを掲げたわけではありません。ただ、先ほどの男性育休の話もそうですし、コロナ禍で職員から出てきたアイデアを「まず、やってみよう」と積極的に採用し続けた結果、「自分たちが何をやりたいかを考え、提案していいんだ」という雰囲気が自然に醸成されていったのかもしれません。
職員が「やらされる」のではなく、「主体的に動く」環境を整え、新しいアイデアを歓迎する。時差出勤も導入していますが、育児や介護だけでなく、趣味を充実させるために積極的に活用する──そうした多様なライフスタイルを許容する風土。こうした心理的な安全性が、組織全体の変革をドライブする上で不可欠だと考えています。
政治家は「民主主義における住民の道具」である
小田 市長のリーダーシップの根底には、どのような政治哲学があるのでしょうか。
田辺市長 私は、政治家は「民主主義における住民の道具にすぎない」と思っています。住民が抱える課題を解決し、より良い社会を実現するための「道具」。それが私の自己認識です。
小田 「道具」ですか。非常にユニークな表現ですね。
田辺市長 道具は、使いたいときに手元になければ意味がありませんよね。だからこそ、私は住民の皆さんにできるだけ近づき、身近な存在であろうと努めています。
例えば、地域の夏祭りや餅つきには、招待状がなくても日程を調べて顔を出します。人手が足りていなければ、率先して餅もつきますよ。そうすると、最初は遠慮されていたのが、翌年からは「市長、なんで来ないんだ」と怒られるようになる(笑)。
でも、それは私という「道具」が「そこにあって当然の存在」と認識してもらえた証拠なんです。
これこそが「民主主義の基本動作」だと、私は本気で考えています。
小田 その哲学は、市民への情報発信にも繋がっていますか? 市長は施政方針演説や広報誌の文章なども、ご自身の言葉で伝えることを非常に重視されています。
田辺市長 「言葉の力」は、政治家にとって最大の財産であり、武器です。その年の市政の理念を伝える施政方針演説の原稿は、今でもすべて自分で一から書いています。以前、道の駅を建設しないという大きな決断をした際も、「なぜつくらないのか」という理由を自分の言葉で書き、全世帯に回覧しました。
賛否のある政策こそ、トップが自らの言葉で、誠実に市民に説明責任を果たす必要がある。その積み重ねが、行政への信頼を築いていくのだと信じています。
「走りながら考える」という実践哲学、有事で試された想像力、そして「住民の道具たれ」という確固たる信念。田辺市長のリーダーシップの根源にあるのは、机上の空論ではなく、現場感覚に裏打ちされた強い意志と覚悟でした。
シェアリングエコノミー、DX、そして後編で詳述する公民連携──この三つの柱は、人口減少社会という現実への処方箋として、「走りながら」辿り着いた必然の選択と言えるでしょう。そして何より、田辺市長は、行政内部の意識改革から始めることで、職員の主体性を引き出し、持続的な変革への基盤を築いてきました。
後編では、この理念を具現化する具体的な官民共創プロジェクトの全貌と、その成功の裏側に迫ります。
インタビュー会場となったこの「快生館」──休業した温泉旅館の再生プロジェクト、そして「半世紀分」とも語る中心市街地活性化計画。数々の挑戦をいかにして成功させたのか、その戦略と未来像をさらに深く掘り下げていきます。
(第3回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年9月22日号
【プロフィール】
 田辺 一城(たなべ・かずき)
田辺 一城(たなべ・かずき)
1980年生まれ。慶大法卒。2003年毎日新聞社に入り、記者として活動。
11年福岡県議選に初当選(15年再選)。18年同県古賀市長選に初当選し、現在2期目。