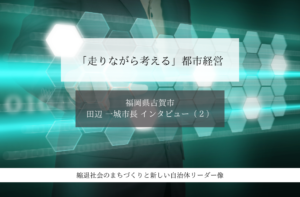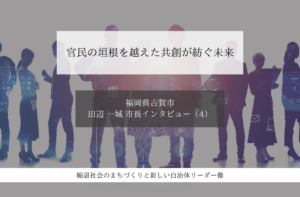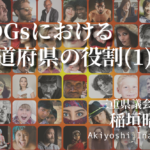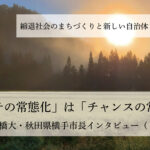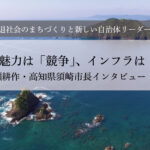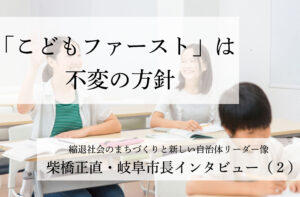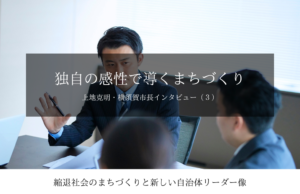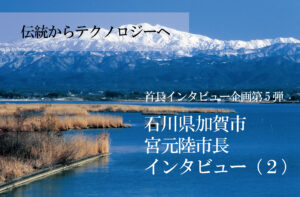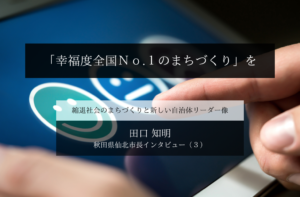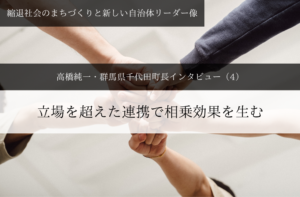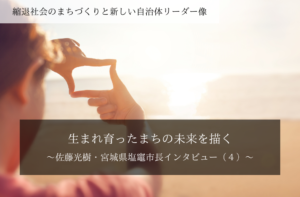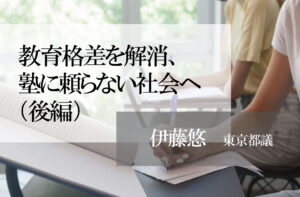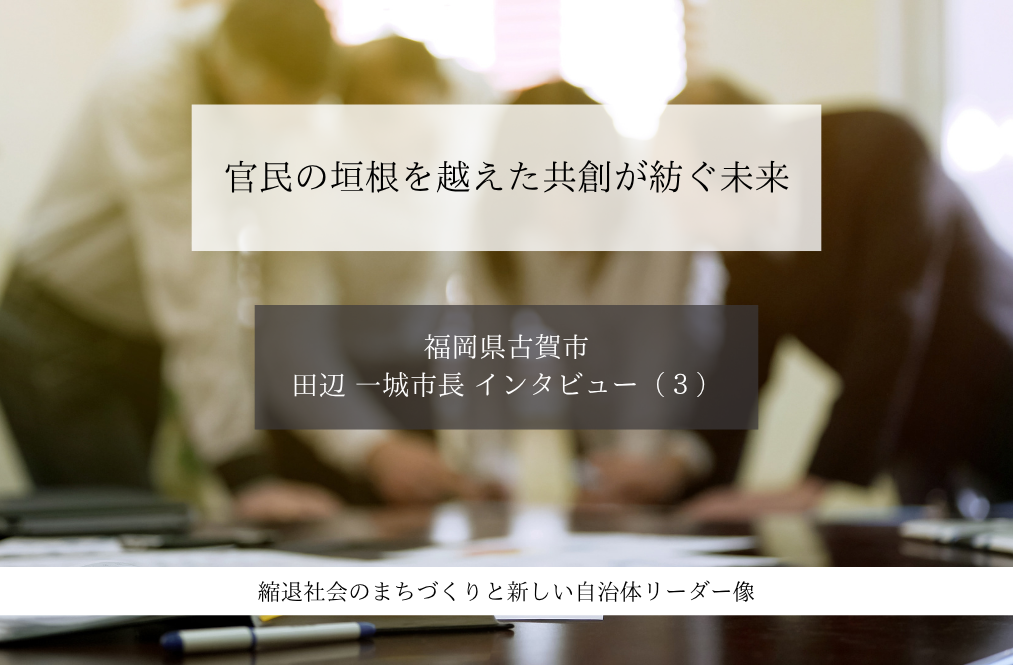
福岡県古賀市長 田辺一城
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/10/29 「走りながら考える」都市経営~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(1)~
2025/10/30 「走りながら考える」都市経営~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(2)~
2025/11/4 官民の垣根を越えた共創が紡ぐ未来~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(3)~
2025/11/6 官民の垣根を越えた共創が紡ぐ未来~田辺一城・福岡県古賀市長インタビュー(4)~
前編では、福岡県古賀市の田辺一城市長が掲げる「走りながら考える」という経営哲学と、シェアリングエコノミーやDX(デジタルトランスフォーメーション)を軸とした組織変革への取り組みを紹介し、行政内部の意識改革から始まった変革の基盤が、いかにして形成されたかが明らかになりました。
後編では、その理念がどのようにして具体的な「共創」プロジェクトとして花開いているのかを詳述します。コロナ禍の「ピンチをチャンスに」変えた快生館プロジェクト、長年の懸案だった中心市街地開発を動かした交渉術、そして行政の常識を覆す「実証実験事業」まで。田辺市長にとって「共創」とは単なる公民連携の手法を超えた、多様な主体への深い信頼に根差した哲学そのものです。
その実践の最前線と、宇宙をも見据える壮大な未来ビジョンを、市長自身の言葉で解き明かしていきます。(聞き手=一般社団法人官民共創未来コンソーシアム代表理事・小田理恵子)
「公民連携」を超えた「共創」という哲学
小田 前編では、古賀市が掲げる三つの柱の一つ「公民連携」についても触れましたが、市長はよく「共創」という言葉を使われますね。この二つにはどのような違いがあるのでしょうか。
田辺市長 「公民連携」は、持続可能な都市経営を進めるための具体的な手段やアプローチを指します。公がきっかけをつくり、民間の知見や力を取り入れて事業を運営する。行政の論理だけでは生まれない、民間の知見や感性を最大限に活かすことです。
一方で「共創」は、それを包含するより上位の哲学だと考えています。単なる公民連携のテクニックではなく、多様な主体への深い信頼とリスペクトに根差した考え方そのものです。古賀市の職員は約400人ですが、市民6万人、さらには世界中の人々と連携すれば、解決できる課題は無限に広がります。
多様な人材の経験、知見、感性をクロスさせることで、社会課題解決の可能性を飛躍的に高める──これが私たちの目指す「共創」なのです。
小田 その哲学が最も分かりやすく体現されているのが、今回のインタビュー会場でもある「快生館」でしょうか。
田辺市長 まさにその通りです。快生館は「共創」の象徴的な事例だと自負しています。
「ピンチをチャンスに」快生館が示す共創の理想形
小田 快生館について、改めて詳しく教えてください。入り放題の温泉付きサテライトオフィスというのは、全国でも類を見ませんね。
田辺市長 ここは薬王寺温泉の源泉がある、地域で愛された老舗旅館でした。しかしコロナ禍の影響で休業を決められたのです。この貴重な地域資源が失われるのは計り知れない損失だと感じ、市としてすぐに動きだしました。
「新しい働き方で、地方に人の流れをつくる拠点にできないか」。そう考え、旅館をサテライトオフィスとしてリノベーションしたのです。まさに「ピンチをチャンスに」変えた象徴的なケースであり、「場のシェア」によって新しい働き方の可能性を広げる試みでした。


インタビューは快生館にて行われた(出典:官民共創未来コンソーシアム)
小田 「快く働き、快く生きる」というコンセプトも印象的です。
田辺市長 スキームとしては「公が主体となり、民間の力を取り入れて運営している」形です。市が場を整備し、運営は民間のプロにお任せする。そうすることで、行政の論理だけでは生まれない、彼らの知見や感性が最大限に活かされます。
おかげさまで運営は5年目を迎え、県内外から多くのワーカーや事業者を受け入れています。(働きながら休暇を楽しむ)「ワーケーション」の実施をきっかけに移住された方も出てきており、コンセプトは着実に根付いています。公がつくったプラットフォームの上で、民間が我々の想定を軽々と超えるような素晴らしい事業を展開してくれる。これこそが、これからの公民連携の理想形であり、「共創」の成果だと考えています。
「対話の力」で動かした半世紀の懸案
小田 快生館のような個別プロジェクトから、さらに大規模な中心市街地開発まで、古賀市の「共創」は多岐にわたります。
田辺市長 はい。この2期8年の任期で「半世紀分のまちづくりを進める」という覚悟で臨んでいます。その最大の核が、古賀駅周辺の再開発です。特に東口エリアは、長年の懸案でした。
以前、担当職員がJR鹿児島線沿線のすべての駅周辺を調査したのですが、広大な低未利用地が残っているのは古賀駅東口だけだったのです。つまり、ここは福岡都市圏における「ラストフロンティア」なんです。
小田 それだけのポテンシャルがありながら、なぜ開発が進まなかったのでしょうか。
田辺市長 やはり、大規模開発に不可欠な地権者の方々との合意形成が難しかったからです。そのため、私は就任直後から、担当者に任せるだけでなく、私自身が意識的、意図的に地権者の方々の元へ足を運びました。相手方のトップや中心となる方と直接会い、「古賀市は本気です。中心市街地で車中心ではない、人を中心とした新しい価値観のまちづくりを一緒にやりましょう」と、私の言葉でビジョンを伝えました。
小田 トップ自らが出向くことで、市の本気度を示したわけですね。
田辺市長 そうです。誠実にコミュニケーションを図ることで信頼関係が生まれ、就任から1年もたたないうちに、最大地権者さんと開発検討の協定締結にこぎ着けました。そして先日、ついに開発の前提となる道路計画の協定を結ぶことができました。これは都市計画における、極めて重要な一歩です。
やはり、物事を動かすのは「意を伝える」こと。その熱量がスピード感にも繋がると実感しています。
小田 西口エリアでも動きが活発化していると伺いました。
田辺市長 西口では、3年間の民間と連携したエリアマネジメント事業を通じて「るるるる」という共創空間が生まれました。これは音楽教室の建物をリノベーションし、シェアキッチンを備えた施設として、新しいお菓子屋さん、カフェ、カレー屋さんなどを始めたい人が、好きな日時にチャレンジできる「場のシェア」の拠点です。
こうしたエリアマネジメントの結果、西口エリアでは空き店舗が次々と新しいお店に生まれ変わるなど、新たな人の流れができて、市の事業でスタートしたものが、現在では民間の自走状態になっています。都市開発だけでなく、既存の資源をより良い形で活かすという「共創」の実践例です。
(第4回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年9月29日号
【プロフィール】
 田辺 一城(たなべ・かずき)
田辺 一城(たなべ・かずき)
1980年生まれ。慶大法卒。2003年毎日新聞社に入り、記者として活動。
11年福岡県議選に初当選(15年再選)。18年同県古賀市長選に初当選し、現在2期目。