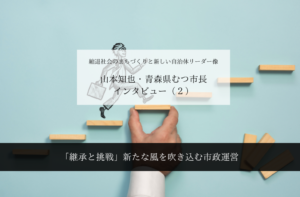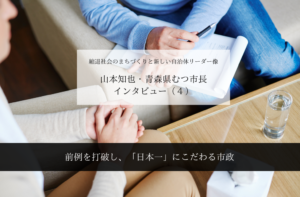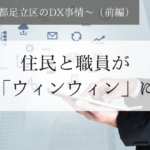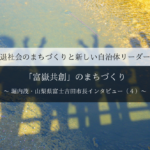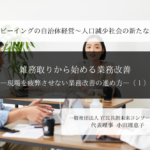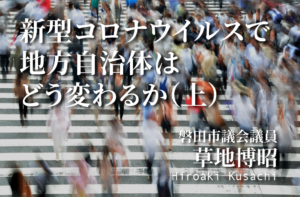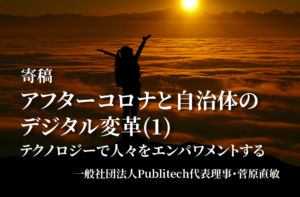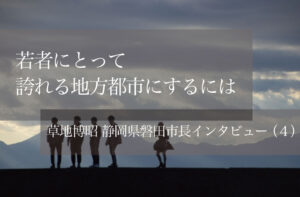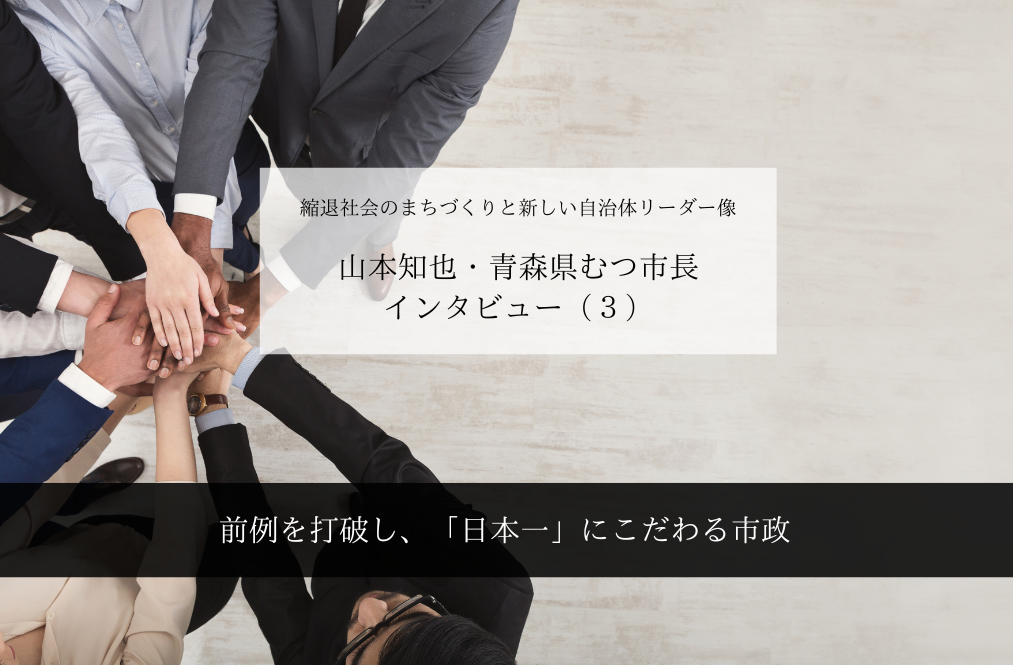
青森県むつ市長・山本知也
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事・小田理恵子
2025/04/23 「継承と挑戦」新たな風を吹き込む市政運営~山本知也・青森県むつ市長インタビュー(1)~
2025/04/24 「継承と挑戦」新たな風を吹き込む市政運営~山本知也・青森県むつ市長インタビュー(2)~
2025/04/30 前例を打破し、「日本一」にこだわる市政~山本知也・青森県むつ市長インタビュー(3)~
2025/05/01 前例を打破し、「日本一」にこだわる市政~山本知也・青森県むつ市長インタビュー(4)~
第1~2回では、「日月に私照なし」を信念とした公平・公正な市政運営や、前例踏襲を打破するために挑戦を続ける山本知也市長の姿勢についてお話を伺いました。
3~4回では、その信念を基盤に展開されている具体的な施策や取り組みに焦点を当てます。DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した地方課題の解決、市民から直接意見を聴く「FLAT─ふらっと─」プロジェクト、そして「日本一」を目指すむつ市の挑戦。
その一つ一つに込められた山本市長の想いをお聞きしました。(聞き手=一般社団法人官民共創未来コンソーシアム代表理事・小田理恵子)
地方自治の未来を切り開くDX推進
小田 むつ市は積極的にDX推進を行っています。具体的にどのような取り組みをなさっているのかお聞かせください。
山本市長 私はオンラインこそが、地方が最も進化できるキーワードだと考えています。そこで市では、デジタル技術を活用して地方特有の課題解決に取り組むことにしました。代表的な事例が、オンライン診療の導入です。現在、市内には大きな病院が少なく、市民が専門的な医療を受けるためには、青森市内の医療機関まで片道2〜3時間、積雪時期には4時間以上かけて通院する必要があります。この深刻な課題に対し、オンライン診療を導入することで、往復4〜8時間もかかっていた通院の負担を大幅に軽減することができました。
小田 通院頻度の高い方や病院に行く時間がとりにくい方にとっては、非常にありがたい仕組みですね。地方創生のカギとなる「オンライン」ですが、高齢者からの理解を得られにくいという課題もあります。むつ市ではどのように対応されているのでしょうか。
山本市長 これまでオフラインが当たり前だった世代にとっては、オンラインに対して抵抗感を示す方が多くいらっしゃいます。そこで単に「オンラインを使ってください」と呼び掛けるのではなく、行政がオンラインを推進することで、市民の皆さんにどのようなメリットがあるのかを具体的に示すことを心掛けています。
小田 オンライン化の推進は、医療分野以外でも成果を挙げているそうですね。 その最たる例が大学誘致です。一般的に、大学誘致は人口10万人以上の都市でないと難しいとされる中、人口約5万人のむつ市が誘致に成功した秘訣を教えてください。
山本市長 人口規模の小さな自治体では、大学側がハード面への投資に二の足を踏むケースがあります。そこでむつ市が場所を準備し、大学側はソフト面の準備だけでいい状況を整えたのです。オンライン授業の普及もあり、大学誘致のハードルを大きく下げることができました。結果として、むつ市には今春三つ目の大学が開校する予定です。人口規模の小さな自治体の大学誘致の数としては最多であり、他の自治体の首長からも「なぜそんなに大学が来るのか」と問い合わせを頂くまでになりました。このように、これまで人口が少ないからできないといわれてきたことに対して、オンラインなどの新しい切り口で挑戦していく。そうした姿勢こそが、若い世代の首長に期待されている役割なのではないかと考えています。
小田 山本市長が語るむつ市や青森の未来のお話を伺っていると、自然と気持ちが明るくなってきますね。従来の慣習を打破し、未来を見据える姿勢が山本市長の市政運営の軸のように感じられます。
山本市長 私は「政治家は未来を語るべきだ」という考え方を大切にしています。過去を振り返ることも重要ですが、それ以上に未来に向けた具体的なビジョンを示すことが必要です。例えば、公共交通の分野でも、自動運転の実証実験に取り組んでいきます。タクシーの減少や路線バスの廃止など、地方の交通網は確実に縮小しています。しかし、それを単なる「縮小」で終わらせるのではなく、自動運転という新しい技術にチャレンジすることで、未来への希望を感じていただきたいのです。
人口減少やさまざまな課題は事実として受け止めなければなりませんが、それ以上に新しい可能性を示し続けることが重要です。毎年新しいことに挑戦し、具体的な成果を示すことで、特に高齢者の方々からも「むつ市は明るい」という声を頂けるようになりました。希望がないと人生は楽しくありません。デジタル技術は、その希望を形にする重要なツールなのです。
小田 むつ市のDX推進は、地方創生の新しいモデルケースとも言えそうです。
山本市長 私たちの取り組みの特徴は、デジタル技術を単なる効率化のツールとしてではなく、地域の可能性を広げる手段として活用している点です。オンライン診療や大学誘致の事例が示すように、これまで「地方だから無理」とされてきた課題に対して、デジタル技術を活用することで新しい解決策を見出すことができます。
地方が抱える課題は深刻ですが、DX推進はそれを乗り越えるポテンシャルを秘めています。デジタル技術を活用しながら、医療、交通、教育といった分野で住民にとって実感できる成果を届ける。それを積み重ねることで、むつ市を「このまちで暮らしてよかった」と感じられる場所にしていきたいと思います。
市民と直接的な情報交換をする場
小田 むつ市の未来を明るくする市政についてお話しいただきました。中でも「市民目線」で市民の皆さんと一緒に新しいむつ市をつくっていきたいという想いから「FLAT─ふらっと─」(※注1)を市長就任直後に開始しています。どういった取り組みなのでしょうか。

市の広報チラシから抜粋(出典:むつ市)
山本市長 この取り組みは、私が就任後に立ち上げた市民との対話の場です。市職員は、窓口業務以外で市民と直接話す機会は多くありません。本来であれば議員が市民の声を集め、行政に届ける役割を担っていますが、行政自身も市民の声を直接聞き、市政に反映させる必要があると考えました。そこで開始したのが「FLAT」です。
最初は市民の声を聴くことを目的にスタートしましたが、実際に始めてみると、むしろ市の政策が市民に十分伝わっていないという課題が見えてきました。例えば「子どもの医療費を無償化してほしい」との要望に対して、「既に実施していますよ」と説明する機会も多々あります。結果として、現在では市民の声を聴く場であると同時に、市の政策を直接説明する場としても機能しています。
(※注1)市民との対話を重視し、市長や職員が地域を訪問して直接意見を聴く取り組み。名前には「気軽に意見を発信できる市政」の思いが込められている。
小田 職員の方々は「FLAT」にどのように参加されているのでしょうか。
山本市長 「FLAT」には私だけでなく、必ず部長級職員と若手職員も帯同します。市長の単独参加ですと、私が「市民からこういう声がありました」と職員に伝えても、職員は「市長が聴いた話」とやや人ごとに捉えがちになります。しかし、現場で同じ声を聴いた職員がいることで、政策立案時の説得力が全く違ってくるため、常に職員が同行する仕組みをつくりました。
例えば、先日の物価高騰対策を検討する際の出来事です。国からの交付金約2億円の使い道について、多くの自治体は燃料券や商品券の配布を検討していました。しかし、「FLAT」での対話の中で、主婦の方々から「ゴミ袋の価格が高いので配布してほしい」という声が多数ありました。同席していた部長も、この生の声を聴いていたことで、「確かにゴミ袋について多くの要望がありましたよね」と即座に賛同し、スピーディーな政策実現につながりました。
資料で読むのと実際に現場で聴くのとでは、全く重みが違います。そのため、職員には納得感を持って政策を進めてほしいと考えています。「やれと言われたから」という受け身の姿勢ではなく、自分たちで課題を見つけ、解決策を考える。そのためにも、市民の声を直接聞く機会が不可欠だと考えています。
小田 市民の意見を聴く場であると同時に、職員が高いモチベーションで仕事ができる環境づくりにもなっているのですね。若手職員の同行も、成長を期待してという意図があるのでしょうか。
山本市長 はい、次世代リーダー育成の側面が大きいですね。若手職員は通常、窓口業務や内部の事務作業が中心で、市民と直接対話する機会が限られています。「FLAT」を通じて市民の生の声に触れることで、市職員としての成長を促したいと考えています。
また、「FLAT」は市民との対話だけでなく、職員同士のコミュニケーションの場としても機能しています。部長級と若手職員が同じ目線で市民の声を聴き、意見を交わすことで、組織内の風通しも良くなってきました。これは、働きやすい職場環境づくりにもつながっています。
小田 同じく市民への情報発信という側面では、YouTubeチャンネル「むつ市長の62ちゃんねる」も注目されています。
山本市長 62ちゃんねるは、前市長から引き継いだ重要な情報発信ツールです。就任後、さらなる品質向上を目指し、今年度から制作の外注化を進めています。これは、担当職員が異動するたびに品質が変わることを避け、安定した情報発信を維持するための判断でした。
小田 むつ市はYouTubeをはじめ、さまざまなSNS媒体で積極的に発信をされていますが、どういった狙いがあるのでしょうか。
山本市長 情報媒体の多様化が進む中、情報発信の手段も広げていく必要があります。広報誌だけでなく、FacebookやInstagramのほかYouTubeなど、世代に応じたさまざまな媒体を活用することで、より多くの市民に確実に情報が届くよう工夫しています。
特に20代の若者はInstagramを中心に利用している一方、40〜60代はFacebookの利用が多い、というように世代によって情報収集の手段が異なります。こうした動向を常にキャッチアップし、より良い方法で市民に情報を発信できるように努めています。
小田 「FLAT」での市民との対話や、「62ちゃんねる」での情報発信を通じて、市政はどのように変化しているとお感じですか。
山本市長 最も大きな変化は、市民の声を「聴く」だけでなく、それを確実に政策に反映させる仕組みが出来上がってきたことです。「FLAT」での対話は議事録として残し、市民への回答と共に公表しています。また、市役所内で共有することで、組織全体の政策立案能力の向上にもつながっています。
私たちが目指しているのは、市民一人ひとりの声に寄り添い、それを市政に反映させる行政です。そのためには、職員自身が市民との接点を持ち、課題を肌で感じることが重要です。これからも、さまざまな形で市民との対話を続け、より良いむつ市をつくっていきたいと考えています。
(第4回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2024年3月24日号
【プロフィール】

山本 知也(やまもと・ともや)
1983年青森県むつ市生まれ。
2006年にむつ市役所へ入庁し、体育施設管理、税務、財政、企画や秘書など幅広い業務を担当。
19年、青森県議会議員に初当選し、むつ市を取り巻く課題解決に尽力。23年4月、むつ市長に就任。現在は1期目。