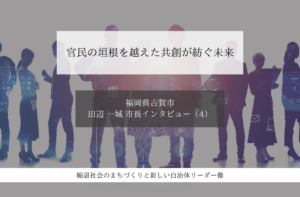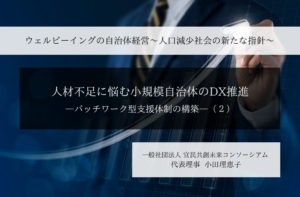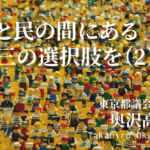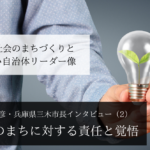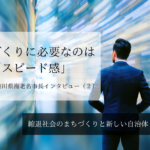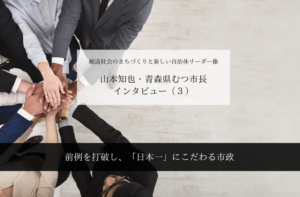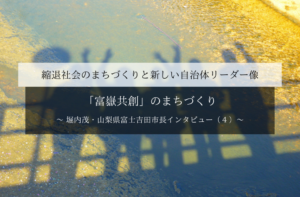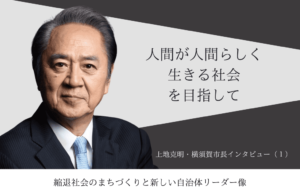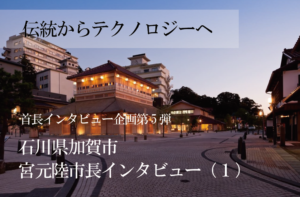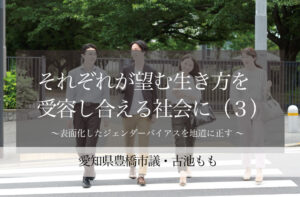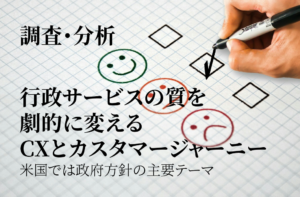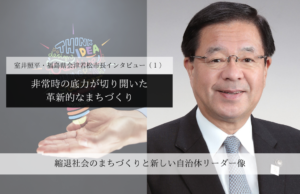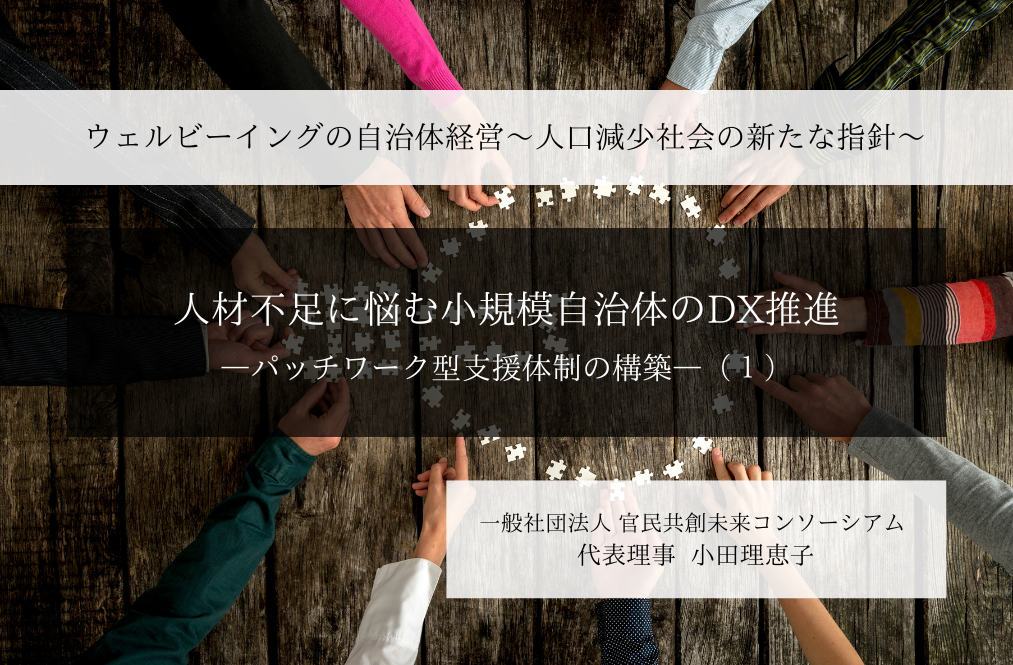
2025/11/25 人材不足に悩む小規模自治体のDX推進-パッチワーク型支援体制の構築- ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(1)~
2025/11/27 人材不足に悩む小規模自治体のDX推進-パッチワーク型支援体制の構築- ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(2)~
地方自治体がより良い住民サービスを提供するためには、行政組織と職員が健全かつ持続可能な状態を維持することが不可欠です。本連載では、ウェルビーイングの自治体経営をテーマに、ストレスのない職場環境、ワーク・ライフ・バランス、そして職員一人ひとりが効率的に業務を進め、成果を実感しながら充実した働き方を実現する手法などを紹介します。
今回は自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するデジタル人材の確保策についてです。
はじめに
人口減少が加速する現代日本において、自治体が直面する課題は極めて深刻です。限られた人的リソースで従来と同水準の行政サービスを維持することは、もはや不可能に近い状況となっています。
自治体に残された選択肢は明確です。反復性の高い業務を効率化・自動化し、貴重な人的資源を付加価値の高い業務に集中投下すること。その実現の前提となるのが、行政のデジタル化、すなわちDXです。
DXは単なる業務改善手法ではありません。人口減少下における自治体の生存戦略と言っても過言ではなく、これを進めないことは行政サービスの維持を諦める「ギブアップ宣言」に等しいものです。従って、自治体がDXを推進することは選択の余地のない必然的な取り組みとなっています。
自治体DXにおける専門人材の重要性
現在、自治体DXは高度な専門性を要するため、外部人材を確保して職員との共同で実施するのが一般的です。CDO(最高デジタル責任者)やデジタル専門官、デジタル人材の派遣などを通じて、民間の外部人材が各地の自治体で活躍しています。
なぜ高度な専門性が必要なのか
自治体DXが専門性を要求する理由は複層的です。
技術的側面では、クラウド基盤の選定、API連携による庁内システムの統合、セキュリティ要件の策定など、ICT分野の最新動向を踏まえた判断が必要です。
同時に行政特有の制約も考慮しなければなりません。地方自治法に基づく事務処理、個人情報保護法制への対応、会計法令に準拠した調達手続きなど、民間企業とは大きく異なる要件への理解が不可欠です。
さらに国の政策動向も重要な要素です。デジタル庁の標準化方針、マイナンバーカード活用推進、自治体情報システムの標準化・共通化といった国策との整合性を保ちながら、自治体独自の課題解決を図る必要があります。
これらの知識と経験を兼ね備えた人材の確保により、多くの自治体でDX推進が着実に進展しています。
小規模自治体が直面する深刻な人材確保課題
しかし、すべての自治体がこうした専門人材を確保できているわけではありません。特に小規模自治体(人口5万人未満程度)ほど人材確保が困難となり、DXを効果的に推進できず、他の自治体に後れを取っている状況が続いています。
「ワンオペ」状態の構造的問題
この格差の背景には、単なる人材不足以上の構造的問題があります。小規模自治体では、DX担当者が1人で複数の業務を抱える「ワンオペ」状態が常態化しており、この担当者をサポートする常勤の専門人材が不可欠となっています。
小規模自治体では、担当者1人が複数の業務を抱えており、対象業務範囲が異常に広いという構造的な問題があります。
具体例を挙げましょう。筆者が知る、ある人口3万人の町のDX担当者は、DX推進計画の策定と実装を担当し、「書かない窓口」や文書管理システムの導入を手掛けていました。同時に、原課からの業務改善相談を一手に引き受け、民間企業との協働や実証実験などの首長案件も担当しています。
さらに翌年には総合計画改定が上乗せされ、地域活動として地元の祭りやイベントへの手伝いに加え、消防団活動まで行っていました。これは到底1人で実施できる業務量ではありません。しかし、これが地方自治体の偽らざる現実です。
なぜ小規模自治体に常勤人材が必要なのでしょうか。
- 第一に、担当者の業務過多により、外部人材への質問や相談に充てる時間が極めて限られていることです。「これはどうすればいいか」「予算はいつまでに提出すべきか」といった頻繁な確認作業は、非常勤の外部人材では対応し切れません。
- 第二に、小規模自治体では庁内の意思決定や調整に時間を要するケースが多く、外部人材が断続的に関わるだけでは、プロジェクトの推進力が維持できません。
- 第三に、システム導入後の運用・保守段階でも継続的なサポートが必要です。小規模自治体では専任のシステム管理者を置くことが困難なため、常勤の専門人材が長期的な運用支援を担う必要があります。
求められる「自律型人材」
こうした環境では、大規模自治体以上に高度な「自律型人材」としての能力が求められます。大規模自治体では複数の職員がDX推進に関わるため、外部人材と職員の協働により知識やスキルを補完できます。一方、小規模自治体では限られた人数で全ての業務をカバーしなければならないため、より幅広い専門性と自律的な判断能力が必要となります。
ここでいう自律型人材とは、自治体DXの全体像を理解し、国の動向を踏まえて現在優先すべき取り組みを適切に助言できる能力を持つ人材のことです。さらに、ベンダーやサービスの選定と調達を主体的に行い、適正価格と仕様を見極めて調達要件に落とし込み、ベンダーとの交渉を担うことができなければなりません。加えて、都道府県などとの共同化や共同調達との連携調整、庁内ステークホルダーへの説明と承認取り付けなど、広範囲にわたる知識と経験が必要です(注1)。
注1=筆者の経験では、適切な支援環境が整備されている場合、民間ICT人材であっても一定規模の自治体での経験を経ればおおむね2年程度で自律型人材として機能するようになると理解しております。しかし、小規模自治体においては育成期間中の業務遂行リスクを考慮すると、現実的な選択肢とは言い難いのが実情です。
確保困難な現実
こうした人材は極めて希少な存在です。ICT技術に精通しているだけでは不十分で、自治体独自の業務やネットワークの仕様、自治体の組織運営、意思決定プロセスなど政策形成に関する深い理解が必要だからです。実際のところ、このレベルの人材は既に他の自治体での業務に従事しており、新たに常勤で確保することは極めて困難な状況にあります。
需要に対して供給が圧倒的に不足しているため、人件費も高騰しており、小規模自治体には常勤で雇用する財政的余力がないのが実情です。一方で、非常勤であれば確保の可能性があります。優秀な自律型人材の多くは、複数の自治体案件を同時並行で手掛けることで、限られた時間をより多くの地域のDX推進に配分する合理的な働き方を選択しているからです。
需要に対して供給が圧倒的に不足している上、常勤雇用の場合、他案件からの収入を失うリスクへの補償として人件費がさらに押し上げられます。高度デジタル人材の多くは複数案件を並行して手掛けることでリスク分散を図っており、非常勤であれば比較的確保しやすい時間単価で対応可能です。しかし常勤雇用の場合、他案件からの収入を失うリスクへの補償として、小規模自治体には負担困難な高額な年収を要求されるケースが一般的です。
さらに、優秀な人材ほど複数自治体への貢献を志向する傾向があり、そもそも常勤での働き方を望まないという根本的な問題もあります。
(第2回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年10月6日号