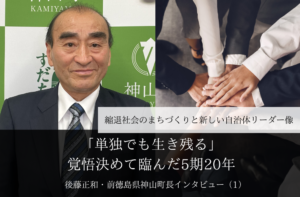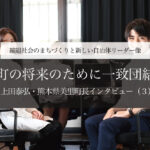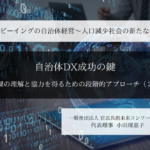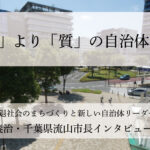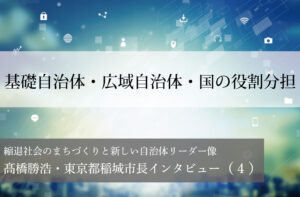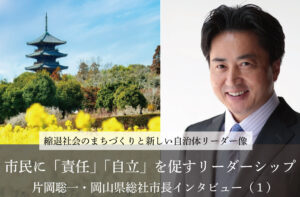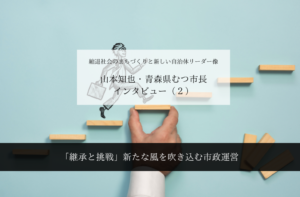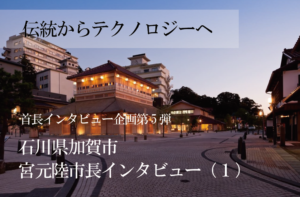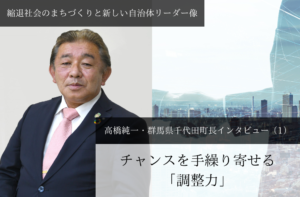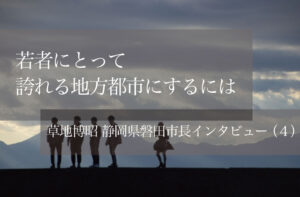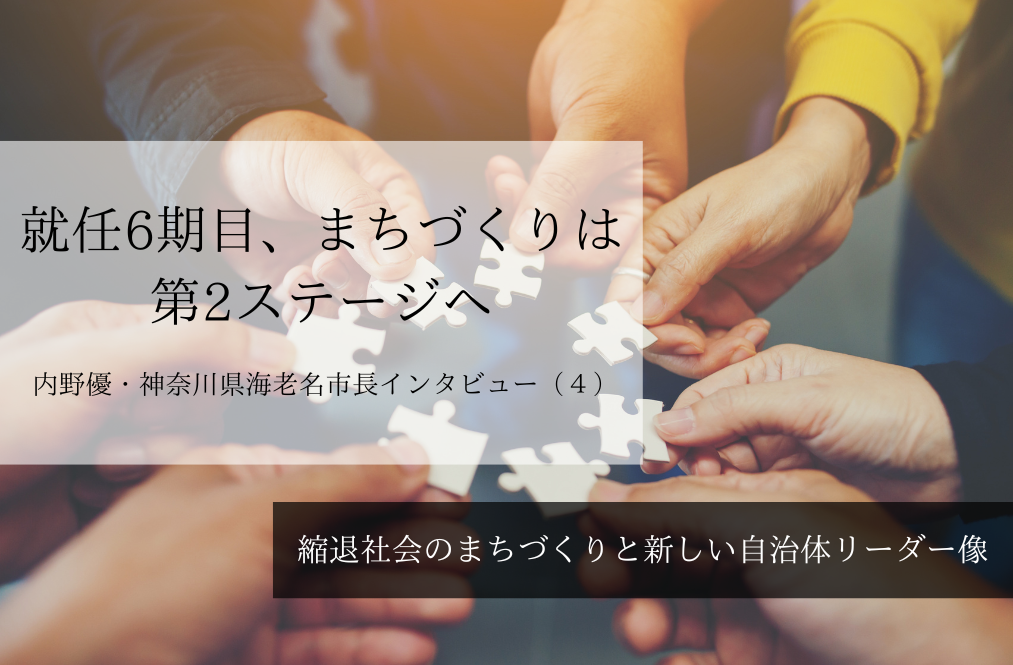
神奈川県海老名市長・内野優
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2024/06/11 まちづくりに必要なのは「スピード感」~ 内野優・神奈川県海老名市長インタビュー(1)~
2024/06/13 まちづくりに必要なのは「スピード感」~ 内野優・神奈川県海老名市長インタビュー(2)~
2024/06/18 就任6期目、まちづくりは第2ステージへ~内野優・神奈川県海老名市長インタビュー(3)~
2024/06/20 就任6期目、まちづくりは第2ステージへ~内野優・神奈川県海老名市長インタビュー(4)~
「住民主体」が行政の本質
小田 海老名市は「ちょっと都会、ちょっと田舎」というキャッチフレーズで親しまれています。これに沿うような取り組みもされているのですか?
内野市長 ソフト面の話になりますが、12年度に窓口改革を行いました。総合窓口とコンシェルジュを設置し、市庁舎を訪れた方に声を掛け、適切な窓口まで案内するようにしたのです。市民の皆さんに「まちが発展しても、海老名市の職員は親切に対応してくれる」と思っていただける体制づくりを目指しました。
小田 近年はデジタルトランスフォーメーション(DX)の文脈で総合窓口を設置する自治体が増えてきていますが、海老名市は12年度の時点で取り組まれたのですね。
内野市長 こちらから「何かお困りですか?」と気配りすること、つまり住民主体であることは行政の本質だと思います。
小田 どの取り組みもスピーディーに実行されているように感じます。なぜ、そのようにできるのでしょうか。他自治体では旧態依然としたやり方を変えたくても、なかなか変わらないという話をよく耳にします。
内野市長 何をするにしても、上意下達だけで物事は動きません。発想の柔軟な若い職員を巻き込み、推進本部などを設ける必要があります。いわゆる体制づくりです。DXは海老名市も取り組みましたが、視察や勉強会に手を挙げたやる気のある若手を巻き込み、全庁横断型の体制で進めました。
小田 若手の取り組みが幹部に理解されず、頓挫するという話もよく耳にします。海老名市では、そうしたことは起こらないのですか?
内野市長 海老名市は、庁議の代わりに「最高経営会議」を設置しています(第2回参照)。そこは私と副市長、そして全部長が政策の意思決定を行う場です。最高経営会議には各部課でもまれ、創意工夫された案が上がってくるような体制になっていますから、幹部の個人的な感情で若手の取り組みがつぶされるようなことはありません。
小田 そのような体制であれば組織としての意思決定がスピーディーに行えるため、タスクフォースにも対応できますね。
広域連携でスケールメリットを生かす
小田 内野市長が先ほど述べられた、まちづくりの第2ステージについて伺います。今後の展望は、どのようにお考えですか?
内野市長 県央地域(相模原、厚木、大和、海老名、座間、綾瀬、愛川、清川の6市1町1村)の人口と経済力は、とても大きなものです。相模原市は政令市ですが、それ以外の市町村も仮にまとまるとしたら政令市の基準を満たします。それくらいのスケールメリットがある地域なのです。少子高齢化という大前提に立って将来を考えると、合併まではいかないにしても、インフラを共有して行政運営の効率化を図った方が良いと私は考えます。
小田 自治体の枠を超えた広域化の重要性は増していると私も感じます。近隣自治体とは、そのようなお話を既にされているのですか?
内野市長 大和、座間、綾瀬の3市長と共に「大和高座広域連携懇談会」を定期的に開催し、広域化について意見交換しています。これまでに急速充電器の設置、ごみ処理、消防の指令システム、DXなどが議題に上がっています。DXに関しては、県央地域の10市町村で協議会が立ち上がっており、良いものは共有しようという話をしています。自治体ごとに入札してシステムを選定するのは非効率ですし、コストもかかります。広域化した方がスケールメリットがあります。
小田 非常に合理的な考え方だと思います。
内野市長 大和、座間、綾瀬、海老名の4市で人口は50万人を超えます。1市ずつではなく、50万人規模でできることを一緒にやっていきましょうと申し合わせています。それが他自治体を巻き込み、さらなる広域化のきっかけとなります。
小田 広域化を進めるための秘訣は何だと思われますか?
内野市長 「私のまちはここからここまで」という境界線の意識をなくすことではないでしょうか。特に学校の立地を見ていると、そう感じます。隣接する自治体の境界付近に、それぞれの自治体が管轄する学校が建っているケースがあると思います。これから少子高齢化・人口減少の社会に突入すると分かっているのならば、統合した方が良いでしょう。
小田 これからの海老名市は、広域化によるまちづくりがテーマになるのですね。
内野市長 個人的な構想ではありますが、大人数が収容できるアリーナを県央地域に整備したいと考えています。スポーツの試合やコンサートが開催できるような施設です。今はそれぞれの自治体が1000〜1500人を収容できる文化会館などを持っていますが、その規模だとプロスポーツや有名アーティストの招致が難しいのです。5000〜1万人規模の会場を複数の自治体が協力して整備できると良いと考えています。
小田 広域化によって「50万人規模のエリア」と捉えると、実現可能性が高いですね。
内野市長 立地については交通利便性を考えて自治体間で協議する必要がありますが、可能性はあると思います。
小田 来年も変化する海老名が見られるのですね。とても楽しみです。
内野市長 まちづくりの第2ステージは、芸術・文化に触れられる環境づくりです。これからの時代は、芸術・文化の発展が住民の皆さんの心の豊かさや潤いにつながってくると思います。これらが実感できるまちづくりを推進していきます。
【編集後記】
なぜ内野市長は、まちづくりのスピード感にこだわるのか。その根底にあるのは「まちが良くなる姿を少しでも早く見せたい」という住民への思いでした。
「住民主体のまちづくり」という考え方は、近年におけるDXの潮流で、ようやく国内にも浸透し始めましたが、内野市長は就任当初からその姿勢を貫いてきました。それが「1年ごとに様変わりするまち」という、目に見える成果として表れているのだと感じました。
スピードを追求することは一見、シビアに捉えられがちですが、価値提供の責任を果たすという姿勢の表れでもあります。人口減少と少子高齢化が待ったなしで訪れる近い将来、自治体経営の在り方の一つとして「スピード」が重視される日も遠くはありません。
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2024年5月13日号
【プロフィール】

内野 優(うちの・まさる)
1955年神奈川県海老名市生まれ。専修大法卒。78年海老名市役所に奉職。83年10月から海老名市議を4期務める。
2003年12月海老名市長に就任し、現在6期目。