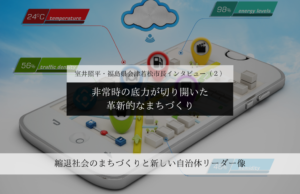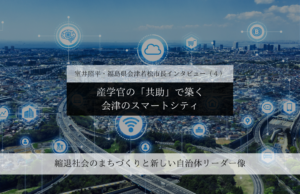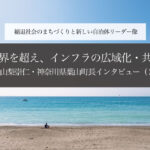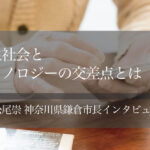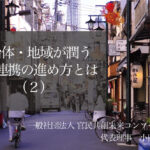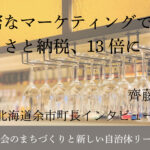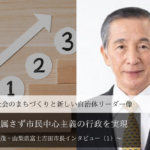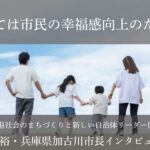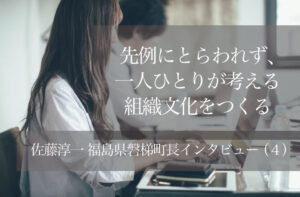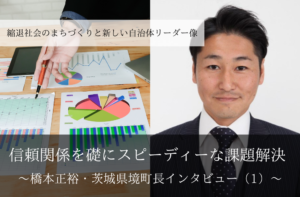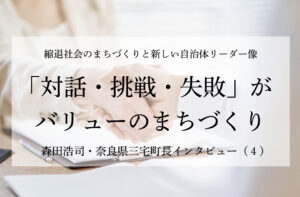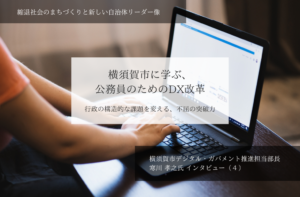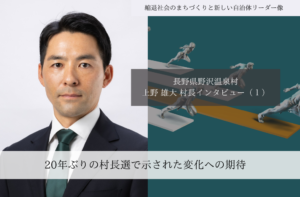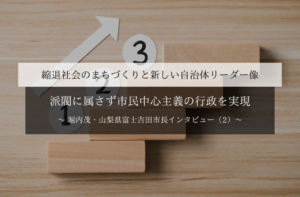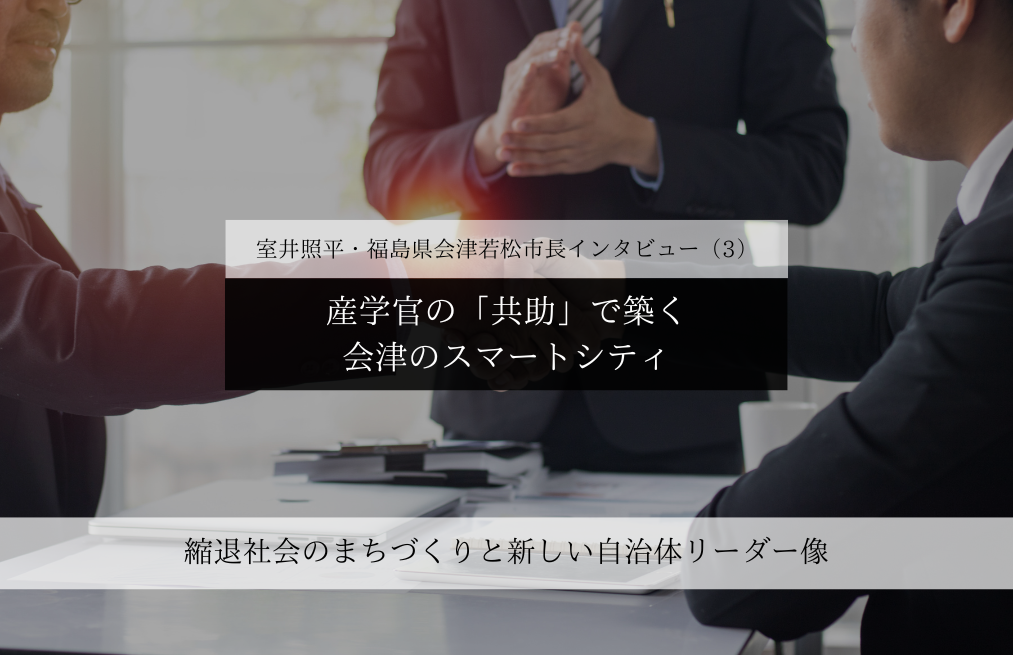
福島県会津若松市長・室井照平
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事・小田理恵子
2025/01/29 非常時の底力が切り開いた、革新的なまちづくり~室井照平・福島県会津若松市長インタビュー(1)~
2025/01/30 非常時の底力が切り開いた、革新的なまちづくり~室井照平・福島県会津若松市長インタビュー(2)~
2025/02/04 産学官の「共助」で築く、会津のスマートシティ~室井照平・福島県会津若松市長インタビュー(3)~
2025/02/06 産学官の「共助」で築く、会津のスマートシティ~室井照平・福島県会津若松市長インタビュー(4)~
ICT(情報通信技術)関連企業の集積拠点「スマートシティAiCT」を核とした会津若松市の取り組みは、地域に根差した新たな官民連携モデルとして注目されています。
市が公共性と透明性を確保し、企業群が収益性と公共性のバランスを取る「共助」の仕組みは、デジタル庁からも推奨される存在に。会津大の知見とICT人材の厚みを生かしながら、デジタル技術の恩恵を確実に地域に還元していく──。
「三方よし」の理念で持続可能な地域づくりを目指す室井市長の哲学と展望を、引き続き伺ってまいります。(聞き手=一般社団法人官民共創未来コンソーシアム代表理事・小田理恵子)


室井市長(上)へのインタビューはオンラインで行われた(出典:官民共創未来コンソーシアム)
「スマートシティAiCT」から広がる会津モデル
小田 スマートシティ会津若松の一環であり、2019年に開始された「スマートシティAiCT」の取り組みについて、詳しくお聞かせください。
室井市長 まず、「スマートシティ会津若松」は11年から始まった本市のデジタル化推進プロジェクトです。その第1ステージの集大成として19年4月に開設したのが、ICT関連企業の集積拠点「スマートシティAiCT」でした。現在36社が入居しています。さらに、この施設を拠点に誘致企業と地元企業が連携して「一般社団法人AiCTコンソーシアム」を設立。約90社が参画し、首都圏企業と地元企業による地域活性化の取り組みをマネジメントする組織として機能しています。
この企業集積は、かつて富士通が立地していた時代からの産業基盤を生かしています。半導体製造装置関連企業も相次いで立地し、人口減少地域における新たな産業基盤として着実に集積が進んでいます。
小田 行政と民間、それぞれの強みを生かしながら、新しい形の官民連携を実現されているわけですね。スマートシティ推進において、「共助」を重視されているとのことですが、具体的にはどのような取り組みを行っているのでしょうか。
室井市長 会津若松市が目指しているのは「共助」のモデルです。これは、従来の行政主導型や民間主導型とは異なる、新しい官民連携の形を目指すものです。
従来型の取り組みには、それぞれ長所と短所があります。民間企業主体の「自助」は、迅速な事業展開が可能である半面、個人情報の取り扱いに対する市民の信頼確保が難しく、また採算性を重視するため社会的に必要な事業であっても実施されにくいという課題があります。
一方、行政主体の「公助」は市民からの信頼は得やすいものの、多様化する市民ニーズへの柔軟な対応が困難で、新規サービスの追加が公費負担の増大につながるというジレンマを抱えています。
そこで会津若松市では、「共助」という新しいアプローチを採用しました。会津若松市は、AiCTコンソーシアムの運営方針や個人情報の取り扱いなどを監督する役割を担い、公共性と透明性を確保します。一方、コンソーシアムは収益性の高い事業と公共性の高い事業をバランスよく組み合わせることで、地域に必要なサービスを持続的に提供していきます。これにより、公共性の確保とビジネスの持続可能性を両立させる新たな官民連携のモデルを構築できました。
小田 AiCTコンソーシアムの設立は、全国的に見ても先駆的な取り組みだったと伺っています。
室井市長 「一般社団法人AiCTコンソーシアム」は、設立からまだ3、4年ほどの組織です。昨今、デジタル田園都市国家構想の推進に伴い、多くの自治体が同様の法人を設立していますが、当時としては画期的な取り組みでした。特に、地元企業と進出企業が協働で地域課題の解決に取り組むというスタイルは、現在デジタル庁からも推奨されているモデルケースとなっています。
しかしこうした活動は、多くの地域で一過性の取り組みにとどまりがちです。一方、会津若松市では「スマートシティAiCT」という物理的な拠点があることで、継続的な取り組みが可能となっています。実際、進出企業から住所を移して定住される方も現れ始め、地域との関係性も着実に深まってきています。
小田 その成果を他地域に展開する動きも始まっているそうですね。
室井市長 はい。AiCTは設立から5周年を迎え、次のステージに向けた準備を進めています。現在の大きなテーマは、データ連携基盤を含めた「会津モデル」を日本全体に展開していくことです。既に福島県が連携基盤を導入し、県内の多くの市町村との接続が進んでいます。今後は、この基盤を通じてさまざまなデータの連携と活用が進み、新たな価値創造につながることを期待しています。
会津若松市に培われたICTの土壌
小田 スマートシティ推進の背景には、会津若松市の持つICTの基盤が大きく影響しているように思います。その源流はどこにあるのでしょうか。
室井市長 会津若松市のICTへの取り組みは、富士通の存在に始まります。富士通が拠点を置いたことで、多くの技術者が移住し、市外からの人材がまちを支えてくれました。現在も半導体製造装置関連など多くの企業が集積し、ハイテク産業のまちとして変貌を遂げています。ICT関連産業がまちの新たな基盤となったのです。
小田 そうした産業基盤は、市役所の体制にも影響を与えたのではないでしょうか。職員の方々のICTリテラシーも高いと伺いましたが。
室井市長 ICTに強い人材が多いのも、会津若松市の特長と言えるかと思います。市役所内には民間企業の出身者を含め、システム開発経験のある者が多数在籍しており、会津大の卒業生も積極的に受け入れてきました。そうした人材がいることで、現在でもCOBOLなどのプログラミング言語を使って、自前でシステムを開発・運用できるような体制が整っています。
小田 ICTに強い人材が多いというのは大きな強みですね。そうした体制はどのように構築されてきたのでしょうか。
室井市長 特定部署に過度な負担が集中することを避けるため、組織体制は最小限の変更にとどめました。具体的には、既存の情報政策系部署に加え、企画調整課の下にスマートシティ推進室を設置したのです。これは、スマートシティが全庁的な取り組みであり、一部署だけで完結するものではないという考えに基づいています。結果として、職員一人ひとりの積極的な姿勢が、組織全体のICT推進力となりました。
小田 産業基盤と人材基盤に加えて、会津大の存在も大きな特長だと思います。会津大との連携について、お聞かせいただけますでしょうか。
室井市長 会津大はコンピュータ理工学の専門大学であり、スマートシティ推進における最大の知的資源です。私自身、2代目学長とICTの可能性について議論を重ねる中で、大学の知見を地域課題の解決に生かす可能性を探ってきました。さらに、コンサルティング大手のアクセンチュアが加わったことで、その可能性は現実のものとなりました。
人材育成の面でも、大学の存在は欠かせません。会津大の卒業生が市役所や地元企業に就職することで、地域全体のICTリテラシーが向上してきました。また、バックヤードとして大学があることで、「頑張ろう」という機運が生まれ、若手職員の意欲も高まっています。
このように、新しい産業の柱をつくりたいという市の思いと、会津大やアクセンチュアの技術・知見が結び付き、厚みのある人材層が形成されました。それがスマートシティ推進の大きな原動力となっているのです。
(第4回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2024年12月16日号
【プロフィール】
 室井 照平(むろい・しょうへい)
室井 照平(むろい・しょうへい)
1955年生まれ、会津若松市出身。東北大経済学部経営学科卒。
99年から会津若松市議会議員2期、2006年から県議会議員1期を務める。
11年8月に会津若松市長に就任し、現在は4期目。