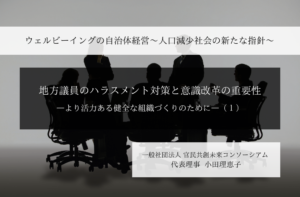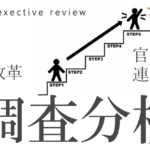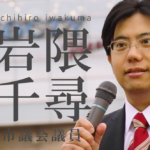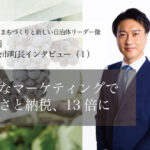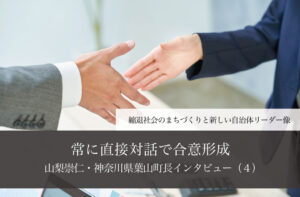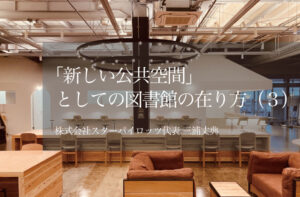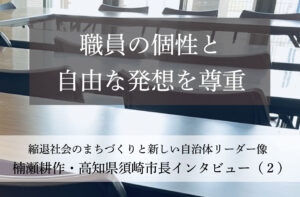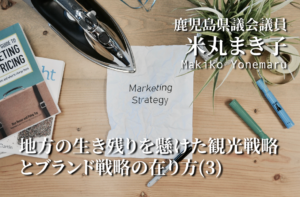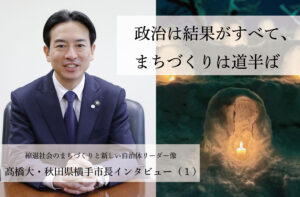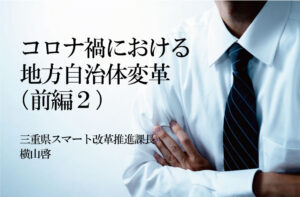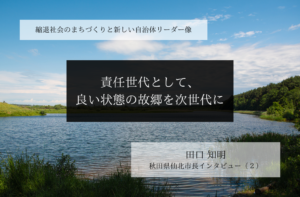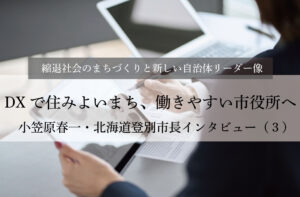北海道名寄市長 加藤剛士
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/08/06 「聞く力」とまちづくりの原点~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(1)~
2025/08/07 「聞く力」とまちづくりの原点~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(2)~
2025/08/12 「保守と斬新」の両輪で拓く名寄の未来~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(3)~
2025/08/14 「保守と斬新」の両輪で拓く名寄の未来~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(4)~
「顔の見える関係」から生まれる協働
小田 「市民との協働」を市政で推進される上で、特に大切にされていることや、何か象徴的な取り組みがございましたらお聞かせいただけますでしょうか。
加藤市長 はい、市民と行政が同じ目標へ力を合わせるには、まず互いを理解し信頼し合える「顔の見える関係」が不可欠です。その上で、名寄市で長年力を入れ、私も大切にしている特徴的な取り組みの一つが、民生委員・児童委員の皆さんとの連携ですね。
小田 民生委員・児童委員の方は、地域住民に最も身近な立場で相談に乗り、行政や専門機関への橋渡しもされるなど、地域福祉において非常に重要な役割を担っていらっしゃいますね。名寄市では具体的にどのような形で連携を進められているのでしょうか。
加藤市長 名寄市では、毎年4月に必ず名寄市民生委員児童委員連絡協議会全体会議を開催し、その後に懇親会を行っています。この懇親会には、私や、市の管理職や一部職員まで約30人の市職員が参加し、100人ほどの民生委員・児童委員の皆さんと文字通りお酒を酌み交わし、ざっくばらんに意見交換する。この形を長年続けています。
小田 それは全国的にも珍しい、非常に積極的で素晴らしい取り組みですね。実際にどのような効果や手応えを感じていらっしゃいますか。
加藤市長 先日、札幌から講演に来られた方がこの懇親会をご覧になり、「これほど多くの職員が民生委員・児童委員の皆さんと共に深く意見交換する場は、他ではあまり見ないですね」と大変感心されていました。
私たちには長年の習慣ですが、「良い取り組みなんだな」と再認識させてくれますね。
何よりも、この場を通じて市職員と、地域福祉の最前線でご尽力くださる民生委員・児童委員さんとの間に、直接的な「顔の見える関係」と揺るぎない「信頼感」が生まれていることが最大の成果です。
前向きでボランティア精神旺盛な民生委員・児童委員の皆さんとの交流は市職員の大きな刺激となり、活発な議論が新たな施策のヒントになることも少なくありません。これこそが、私たちの目指す「協働によるまちづくり」の土台だと考えています。
人口減少への挑戦「選ばれる地域」へ
小田 名寄市も多くの地方都市と同様に、人口減少という大きな課題に直面されているかと思います。この現状を市長はどのように受け止めていらっしゃいますか。
加藤市長 人口減少は地方都市に共通する、避けては通れない大きな課題です。名寄市においても人口減少が急速に進んでいるが故に、私たちが目指すべきまちの姿と現状との間に、少しずつ乖離が生じてきています。今まで通りに行政サービスを提供したり、地域機能を維持したりすることが難しくなってきている事例が、残念ながら散見されるようになっているのが実情です。こうした状況に対応するために、やはり行政の仕事の在り方や公共施設・サービス自体を時代に合わせて変えていかなくてはいけないと感じています。
例えば、行政機能の集約や既存の公共施設の機能を再編、場合によってはこれまで提供してきたサービスをやめていく、といった厳しい判断もやらざるを得ないのかな、と。一方で、名寄市は北北海道の要衝としての責務も果たしていかねばならないと考えています。
小田 行政内部の変革も進めつつ、さらに人口減少に歯止めをかけ、地域活力を維持していくために、現在、名寄市として特に力を入れていらっしゃる具体的な取り組みがございましたらお聞かせください。
加藤市長 人材確保の新たな一手として、国際協力にも力を入れています。具体的には、JICA(国際協力機構)の「草の根技術協力事業」を活用させていただき、特にネパールに焦点を当て、高齢者福祉分野での外国人材受け入れと育成を進めています。
ネパールも将来的には日本と同じように高齢化が進むといわれています。一方で、名寄には福祉を専門に学べる大学があり、介護施設もあるのですが、こちらも人材の確保が本当に厳しい状況でしてね。
ですから、この事業は単に名寄の労働力不足を補うというだけでなく、将来ネパールの福祉を担う人材を名寄で育成し、その知識や経験を母国で活かしてもらう、という「相互協力」の精神を何よりも大切にしています。実際に、先日もネパールから研修生や現地の福祉施設の方々など十数人が名寄を訪れ、2週間ほど滞在して専門的な福祉プログラムを学んでいかれました。

名寄市地域交流プログラム(出典:名寄市Webサイト)
小田 単なる労働力の確保ではなく、国際貢献と人材育成という長期的な視点がおありなのですね。
加藤市長 そこが肝心です。名寄市が「選ばれる地域」として外国人の方々に「ここだったら」と思っていただけるためには、何が必要か。労働条件だけでなく、温かい人間関係、安心できる環境、そして行政と地域一体の受け入れから生まれる「信頼感」や「つながり」をつくっていくことなのではと考えています。現在は介護分野が中心ですが、他職種への拡大も視野に入れています。ここは民間任せにするところが多いのかもしれませんが、国と国との関係性を考えると、私たち行政がある程度主体的に動き、共に汗を流していくことが、これからの時代には非常に大事になってくると思っています。
小田 国際的な人材交流に加え、国内に向けた人材確保や、名寄市の魅力を積極的に発信していくための具体的な取り組みについてもお聞かせいただけますか。
加藤市長 人材確保は緊急性の高い課題と捉え、多角的に取り組んでいます。まず官民連携で「名寄市人材確保対策協議会」を立ち上げました。市内の事業者の皆さんも、人材不足には頭を悩ませていらっしゃいますので、行政と民間が一丸となって名寄の仕事や暮らしの魅力を発信するプラットフォームづくりを推進しているところです。また、外部の専門人材も登用し戦略的な広報活動を強化するとともに、市職員全体の広報意識の向上にも力を入れています。
小田 さまざまな角度から人口減少問題に取り組み、情報発信にも力を入れていらっしゃるのですね。これらの取り組みを通じて、市長が目指す「選ばれる地域・名寄」とは、最終的にどのような姿なのでしょうか。
加藤市長 私が目指す「選ばれる地域」とは、単に人口が増えることではありません。このまちに関わる全ての人々が、名寄の豊かな自然や歴史、文化、人の温かさに触れ、自分らしく安心して心豊かに暮らし、活動できると感じられる。そして何より、未来への希望と可能性を誰もが感じられる、そんな地域です。
「物流拠点構想」交通の要衝・名寄の挑戦
小田 物流の24年問題や交通インフラの維持は、名寄市にとっても大きな課題ですね。「交通の要衝」としての強みを活かし、どのような未来図を描いていらっしゃいますか。
加藤市長 名寄市は豊かな農畜産物の生産地ですが、物流の24年問題もあり、大消費地への輸送手段確保は大きな課題です。「交通の要衝」という、名寄市の地理的特性を最大限活かし、「共同輸送・中継輸送の拠点」整備を考えています。
この構想は、地元の商工会議所と市が長年勉強会を重ね、高速道路の全線開通も見据えています。今後はセミナー開催など準備を進め、「なんとかこれを形にしていきたい」という強い想いで取り組んでいます。多くの関係者との調整は容易ではありませんが、国の力も借りつつ、将来は災害に強い防災拠点としての機能も持たせたいですね。
小田 物流や交通インフラという大きな課題に対し、広域的な視点と強い意志で取り組まれているのですね。最後に、名寄市が北海道の未来、そして次世代に対して果たしていくべき「責任」について、市長のお考えをお聞かせください。
加藤市長 まず現在の地方創生や都市部への一極集中の議論には、もう少し力強さが欲しいと感じています。もちろん、私たち地方自治体が自ら汗を流し、知恵を絞ることが大前提ですが、国や広域自治体による多角的な支援が地域の持続可能性には不可欠だと期待しています。
その中で名寄市は道北の、北海道は日本の重要な拠点です。この地の豊かな自然、先人たちが築き上げてきた文化や産業、そして何よりもここで暮らす人々の生活と笑顔をしっかりと守り、次の世代へとつないでいくこと。それが首長としての「未来への責任」だと考えています。
【編集後記】
加藤市長の市政運営の軸は、市民や職員の声に耳を傾ける「聞く力」と「ボトムアップ型の組織運営」です。その経験に裏打ちされた堅実なマネジメントと、「保守と斬新」を両立させる独自の哲学は、地域に根差した施策を力強く推進しています。この「聞く力」と着実な実行力を併せ持つ市政は、人口減少時代の地方自治に「信頼と共感に基づく地域経営」の新たなモデルを示す可能性を秘めていると言えるでしょう。
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年7月14日号
【プロフィール】

加藤 剛士(かとう・たけし)
1970年11月18日北海道名寄市生まれ。小樽商科大学卒業後、千代田生命保険(現・ジブラルタ生命保険)に勤務。
その後、父が経営するホテル・飲食店グループ「KTバイオニアグループ」に入社し社長を務める。
名寄青年会議所理事などを歴任。2010年、39歳で名寄市長に初当選し、以降無投票を含め4期連続で市長を務める。
全国青年市長会会長も歴任。現在4期目。