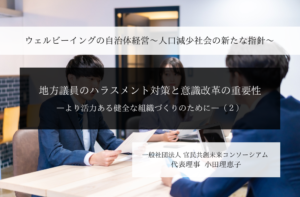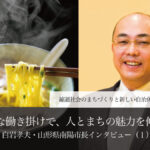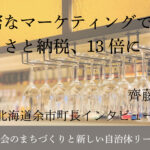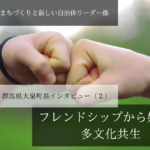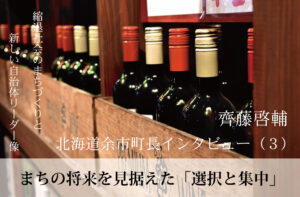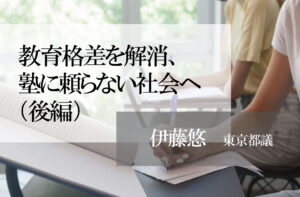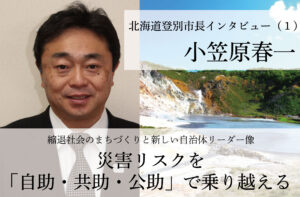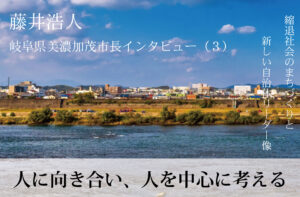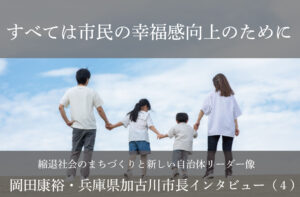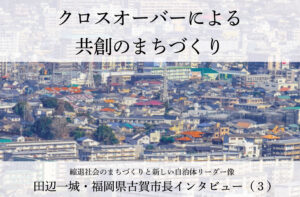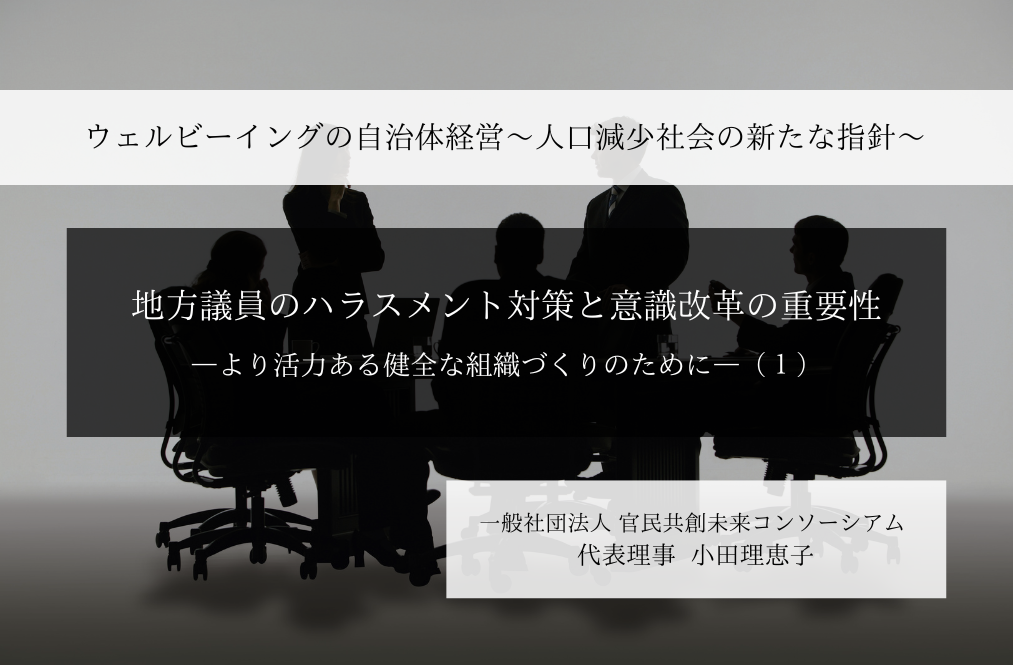
2025/09/03 地方議員のハラスメント対策と意識改革の重要性-より活力ある健全な組織づくりのために- ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(1)~
2025/09/05 地方議員のハラスメント対策と意識改革の重要性-より活力ある健全な組織づくりのために- ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(2)~
地方自治体がより良い住民サービスを提供するためには、行政組織と職員が健全かつ持続可能な状態を維持することが不可欠です。本連載では、ウェルビーイングの自治体経営をテーマに、ストレスのない職場環境、ワーク・ライフ・バランス、そして職員一人ひとりが効率的に業務を進め、成果を実感しながら充実した働き方を実現する手法などを紹介します。
今回は、地方議員のハラスメント対策について取り上げます。
7月上旬、福岡県議会主催の「議会関係ハラスメント根絶のための議員研修」が福岡市内のホテルで開催されました。筆者は講師として地方議会におけるハラスメントの防止についてお話しする機会を頂きました。
この研修は、福岡県議会が2022年に制定したハラスメント防止条例に伴い、県内の市町村議員を対象に毎年実施されているものです。県内の市町村議員約350人が参加し、参院選の期間中にもかかわらず、これだけ多くの議員が参加したことは、ハラスメント防止への意識の高さを物語っています。
近年、職場におけるハラスメントに対する社会の目は厳しさを増し、多くの組織で対策が進められています。しかし、地方自治体において、住民の代表である地方議員によるハラスメントは、今なお根深く、対策が困難な課題として横たわっています。
政治家による不適切な発言や行為がたびたび報道され、その中にはハラスメントに該当するものも含まれており、地方議員についても同様の問題が指摘されています。こうした社会的批判の高まりを背景に、各地の議会では抜本的な対策の必要性が強く認識されるようになりました。
議会の対策を後押しした国の動き
この対策強化の流れを加速させたのが、国の取り組みでした。21年に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が改正され、国および地方公共団体に対してハラスメント防止のための研修実施や相談体制整備等の施策を講じることが義務付けられました(注1)。
この改正により、地方議会に対してセクハラ・マタハラ等への対策、候補者の選定方法の改善、人材育成、ハラスメントへの対応等、さらには実態調査や啓発活動等に積極的に取り組むことが明記され、議会自らがハラスメント対策を主導する責務が明確化されました。
さらに決定打となったのが、内閣府による実態調査です。議員活動や選挙活動中に、有権者や議員等から実際に受けた、または見聞きしたハラスメントを調べたところ、1カ月で1324件もの事例が寄せられました(注2)。
この数字は、地方議会におけるハラスメントが想像以上に深刻で広範囲にわたる問題であることを示しています。
調査結果の公表を受けて、各地の議会には「自分たちの議会でも同様の問題が潜在している可能性がある」という危機感が広がりました。法的責務の明確化と実態の深刻さが相まって、予防的な観点から条例制定に踏み切る議会が増加しました。
(注1)内閣府「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の改正について(概要)」
https://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/pdf/20210616/01.pdf
(注2)内閣府「政治分野におけるハラスメント防止研修教材の作成について」
https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/politics-harassment/1st/pdf/3.pdf
各地で進む地方議会のハラスメント対策
地方議会におけるハラスメント防止の取り組みは全国に波及しています。一般財団法人「地方自治研究機構」の調べによると、議員のハラスメント防止を目的として条例を制定したのは20年に3自治体でしたが、24年には50を超え、その数は今でも増え続けています(注3)。
議員向けのハラスメント研修を実施する議会も増加しています。また、各地の議長会などでも積極的に研修が実施されており、筆者も県の町村議会議長会の総会などで、県内の議長・副議長向けにハラスメント防止に関する講演を行うことがあります。
(注3)地方自治研究機構「首長等や議員によるハラスメントに関する条例」より議員を対象とした条例を抜粋
依然として残る課題と判断の困難さ
しかし、条例制定や研修実施などの制度整備が進む一方で、地方議員によるハラスメントは依然として多く発生しているのが現実です。ハラスメント事案の報道は後を絶たず、制度整備と実際の問題解決との間には大きなギャップが存在しています。
特に難しいのは、職員に対する議員の行為や言動が「市民の負託を実現しようとする正当な議員活動なのか、それともハラスメントなのか」の判断が極めて困難なケースが非常に多いことです。机をたたく、大声を上げるなどの暴力的な行為は明らかにハラスメントですが、より微妙な言動については線引きが曖昧になります。
- 判断が困難な具体例
例えば、議員が職員に対して「住民の要望だから」として通常の業務時間外に何度も連絡を取り、即座の対応を求めるケースがあります。職員は業務範囲を超えた負担を強いられ、特に緊急性が低い場合は過剰なストレスを受けます。しかし、住民の代表として職務を全うするための業務なのか、ハラスメントなのかの線引きが困難です。
また、議員が「この提案を拒否した場合、次の議会で問題にする」「住民に公表する」と暗に脅すような発言をするケースもあります。明確に命令や脅迫の形を取っていないため、表面的には議員としての正当な権限行使に見えてしまいます。
このような判断の難しさが、問題の早期発見や適切な対応を困難にしており、ハラスメント対策の実効性を阻む大きな要因となっています。職員側も「議員活動の一環かもしれない」という迷いから、相談や報告をためらうことが多く、問題が潜在化しやすい構造的課題を抱えているのが現状です。
(第2回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年8月4日号