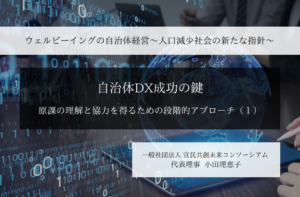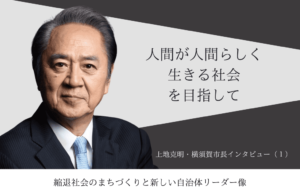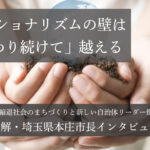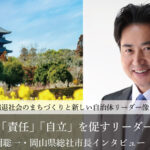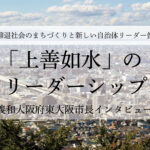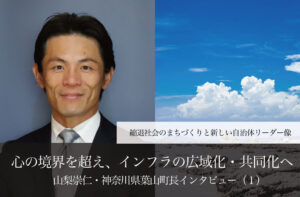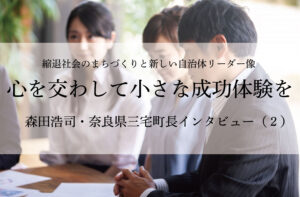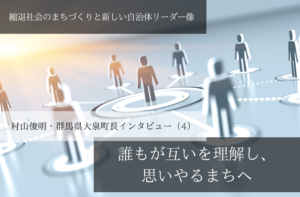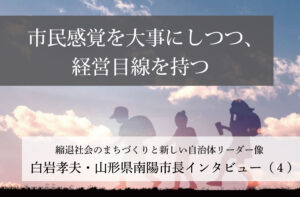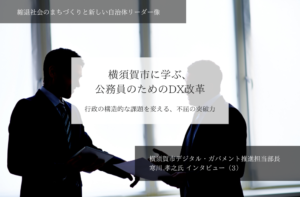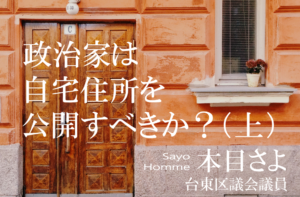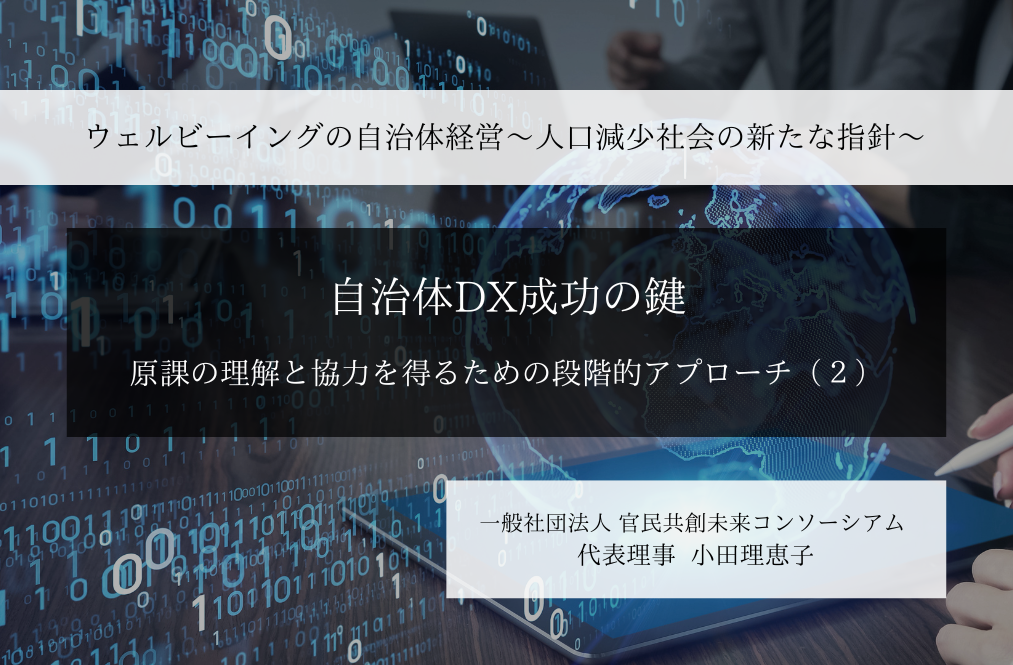
一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事・小田理恵子
2025/05/20 【自治体DX成功の鍵】原課の理解と協力を得るための段階的アプローチ ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(1)~
2025/05/22 【自治体DX成功の鍵】原課の理解と協力を得るための段階的アプローチ ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(2)~
【STEP3 協働】現場の声を吸い上げ、反映する仕組みを構築する
理解者が増えてきたら、次はより積極的に現場の声を吸い上げ、DX施策に反映する仕組みづくりを進める段階です。ここでの「協働」とは、DX担当者と原課が一方通行ではなく、双方向のコミュニケーションを取りながら共に業務改革を進めていくことを意味します。
この段階では、定期的な意見交換会の開催や提案制度の整備、原課職員を含めたワーキンググループ(WG)の設置などが有効です。ある市では、ステップ2で関係構築ができた課から各1人ずつ選出し三つWGを設置。それぞれのWGにはDX担当課が参加して、一緒に課題と解決策を考えています。このように現場の課題やニーズを直接聞く場として活用したところ、「システム改修の際に現場の意見が反映されていない」という不満が明らかになり、システム改修時の要件定義プロセスを見直し、現場の意見を取り入れる仕組みを構築した結果、導入後のシステムに対する満足度が大幅に向上した例もあります。
筆者自身も、自治体から依頼を受け、原課の職員が主体的に業務改善を考えるためのワークショップを実施することがあります。こうしたワークショップでは、普段当たり前のように行っている業務を可視化し、その中の無駄や改善点を発見するプロセスを体験してもらいます。参加者からは「当たり前だと思っていた業務プロセスの中にこんなに改善の余地があった」「他部署の人と話し合うことで新しい視点が得られた」といった声が聞かれ、業務改善に対する意識の変化が見られています。
現場の職員が改善してほしいことやDXに関する提案を吸い上げる仕組みを設けることも有効です。実は業務改善のアイデアは本来現場が一番持っているものですが、日々の業務に追われ「どうしたら仕事が楽になるか」を考える余裕がないことも少なくありません。最初はアイデアがなかなか集まらないかもしれませんが、それは職員が普段から業務をどう改善するかを考えたことがないからです。しかし、現場からの要望に丁寧に対応し続けることで、徐々に「要望を出せば対応してくれる」という理解が広がり、現場が自ら「どうやったら自分の仕事が楽になるか」を考え始めます。そうなると、おのずと改善の機運が醸成されていくのです。
協働のフェーズで重要なのは、現場の声を聴くだけでなく、それが実際の変化につながった事例を積み重ねていくことです。これまでの「改革」では「意見は聞くけど何も変わらない」という経験が多かったため、「自分たちの声が本当に生かされる」という実感を持ってもらうことが鍵となります。
また、協働の過程では現場からの反対意見や懸念の声も多く出てきます。これらを「抵抗勢力」と捉えるのではなく、貴重なフィードバックとして受け止め、共に解決策を考えることが重要です。ステップ2で構築した信頼関係をベースに、より深い協働関係を築くことで、「与えられるDX」から「参画するDX」へと職員の意識が変化し、次の「自律」のステップへの土台を固めることができます。協働の段階では、DX担当者は「実施者」というよりも「支援者」「調整役」としての役割が重要になってきます。
【STEP4 自律】主体的に業務改善に取り組む環境をつくる
最終段階では、原課が自ら業務改善に取り組む環境づくりを目指します。「与えられるDX」から「自ら取り組むDX」へと意識を転換させることが、持続的な変革の鍵となります。
ここまで進んでいる自治体はまだ多くないかもしれませんが、技術環境の変化によって現場主導のDXがより現実的になってきています。特に近年は、AIやノーコードツールの発展により、高度なICT知識がなくても業務システムやアプリの開発が可能になってきました。
例えば、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で業務アプリを構築できるツールや、プログラミング不要でチャットボットを作成できるサービスなど、現場職員でも使いこなせるツールが増えています。このような技術の一般化により、現場でのアプリ開発やシステム改修が十分可能な時代になってきています。
この段階でDX担当部署に求められるのは、必要な権限や予算の移譲、デジタルツールの活用研修、部署横断的な改善事例の共有の場など、自律的な改善活動を支援する体制づくりです。例えば、各部署の「DXリーダー」に小規模な予算決定権を与えることで、軽微な改善策は現場判断で即時実施できる仕組みも効果的でしょう。これにより「決裁を待つ」というボトルネックが解消され、スピード感のある業務改善が可能になります。
また、「ノーコード人材育成プログラム」のような取り組みも有効です。各部署から希望者を募って定期的な研修を実施し、修了者は自部署の業務アプリ開発の中心メンバーとなります。研修終了後も定期的な情報交換会で相互にサポートし合う仕組みがあれば、現場主導の改善活動が持続的に行われるでしょう。
自律のステップにおいては、成功事例を可視化し、組織全体で共有する仕組みも重要です。定期的な「DX成果発表会」を開催し、各部署の取り組みを表彰するとともに、好事例をデータベース化して誰でも参照できる環境を整備することで、「あの部署でうまくいった方法なら、うちでも応用できるかも」という横展開が自然と生まれるようになります。
このステップでは、DX担当部署の役割も大きく変化します。「変革の主導者」から「環境の整備者」「ナレッジの共有者」としての機能が中心となり、現場の自律的な取り組みを後方から支援することが求められます。特に必要なのは、各部署の良い取り組みを見つけ出し、それを組織全体に広げていく「伝道者」としての役割です。
DXの最終的なゴールは、特別な「DX担当」がいなくても、組織全体がデジタルの力を活用しながら常に業務改善に取り組む文化を育むことにあります。自律のステップは、その基盤を作る重要な段階なのです。
最後に
DX推進において原課の理解と協力を得ることは、最も難しくも最も重要な課題です。しかし、この四つのステップを着実に踏んでいくことで、「抵抗勢力」と思われていた部署が「改革の推進者」へと変わる可能性を秘めています。重要なのは、相手の立場に立った改革の進め方です。DXは目的ではなく手段であり、最終的に実現したいのは職員の働きがいと住民サービスの向上です。一朝一夕には進まなくとも、小さな成功と信頼の積み重ねが、組織に確かな変化をもたらすことを信じて、着実に前進していきましょう。
変革は技術からではなく、人の心から始まるのですから。
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年4月7日号