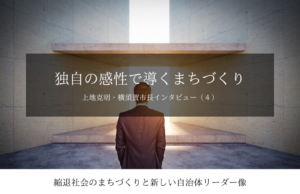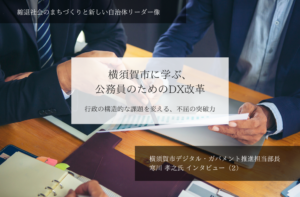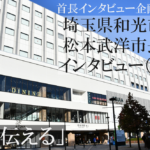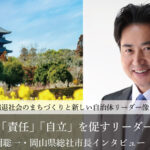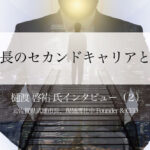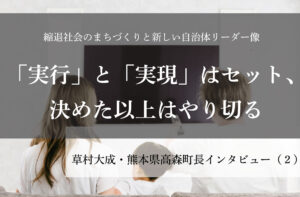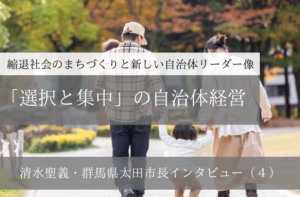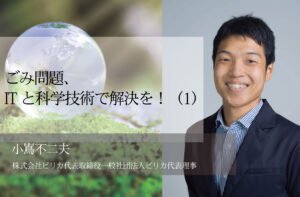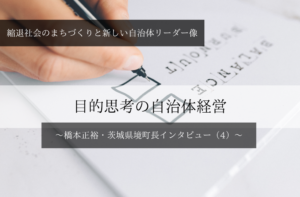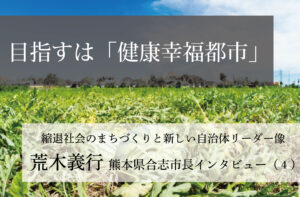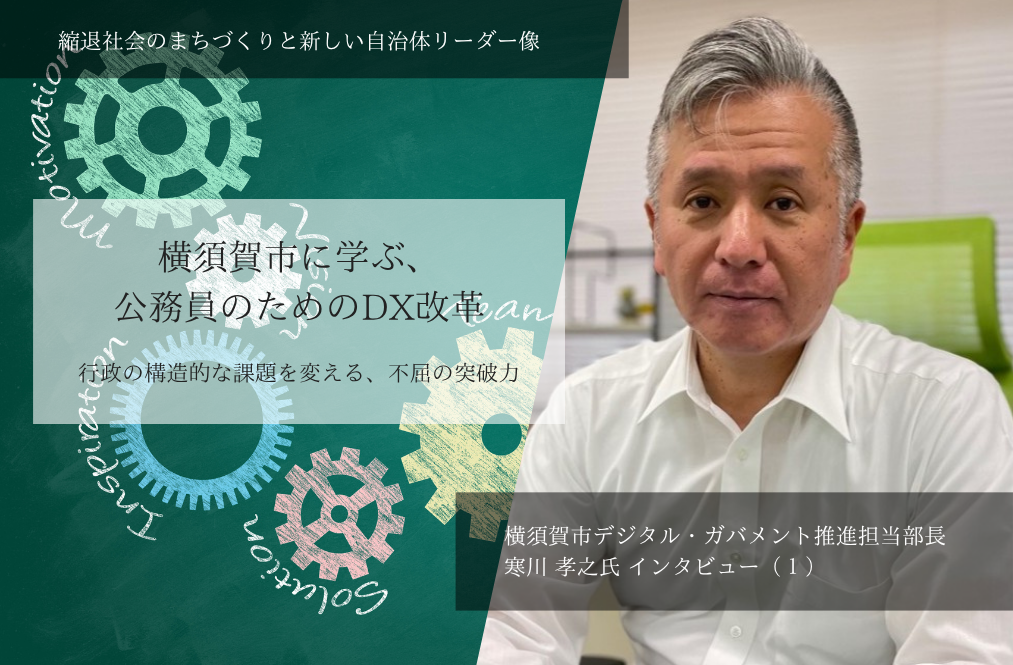
神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長 寒川孝之
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/07/09 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(1)~
2025/07/10 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(2)~
2025/07/15 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(3)~
2025/07/17 横須賀市に学ぶ、公務員のためのDX改革ー行政の構造的な課題を変える、不屈の突破力~寒川孝之・神奈川県横須賀市デジタル・ガバメント推進担当部長インタビュー(4)~
神奈川県横須賀市は、全国に先駆けてChatGPT等の生成AI(人工知能)を全庁的に導入して注目されています。しかし、これは横須賀市のデジタル変革の一側面にすぎません。
横須賀市はDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を「行政の構造改革の最後のチャンス」と位置付け、市役所業務の効率化を追求し、生まれた資源を市民に寄り添う行政に振り向けています。この改革を可能にしているのは、上地克明市長の強いリーダーシップと、市長・副市長・議会の三者が一体となった改革推進体制です。
今回は横須賀市のデジタル・ガバメント推進の実務を担当する寒川孝之氏に、組織変革の現場と、それを支えるリーダーシップについてお話を伺いました。(聞き手=一般社団法人官民共創未来コンソーシアム代表理事・小田理恵子)
「市民に寄り添う」ユニークな市長のリーダーシップ
小田 きょうはお時間を頂き、ありがとうございます。この前、上地市長にインタビューさせていただいたのですが、自治体トップではあまり見掛けないタイプで、興味を持ちました。表現力や言語化する力がすごくアーティスト的ですよね。
寒川氏 ご存じだと思いますが、市長はミュージシャンなのです。また、市長は元議員でもあるのですよ。その前は国会議員の秘書をやっていて、自分の靴をすり減らして地域を駆けずり回ったという、そういう政治活動から、市民に寄り添う姿勢が培われているので、普通の市長とは違うタイプだと思います。
小田 上地市長は紡ぐ言葉が「天から望まれているのだ」といった感じで、一般的な行政や政治家とは異なる哲学と言葉をお持ちで、そこがVUCAの時代に求められるリーダー像なのでは? と感じました。
寒川氏 市役所にはいわゆる前例踏襲の堅い考え方の役人が多かったと思います。でも市長はそういうものを絶対に嫌うのです。「なぜ古い時代に策定された条例に縛られて困っている人を助けないのか」というのが前提にあるので、頭の固い人たちは大変だったと思います。
市長就任後のデジタル化の加速と変革
小田 そんな上地市長が就任してから、横須賀市はデジタル化が積極的に進んでいますよね。寒川さんから見て、上地市長になってからの環境の変化はありましたか?
寒川氏 あります。これまでは「予算の効率、費用対効果の重視」で、限られた財源の中で重点的な部分だけをやっていくという姿勢でした。予算が硬直化していたので、取り組めなかった部分は仕方がなかったのです。
でも上地市長は「必要なところはやらなければいけない」と言って、重点的に予算をつけて攻めていく姿勢があります。そこが今までとは全く違うタイプだと思いました。
小田 市長はそういう判断をロジックで考えているのですか? それとも感性でしょうか?
寒川氏 非常に頭の良い方なので、論理的に考えていると思いますが、感性の部分も確かにあると思います。「困った市民にとにかく手を差し伸べろ」ということをずっと言っていて、その姿勢はぶれていないのです。職員の仕事は入力の仕事ではないと断言していて、「俺は君たちに作業なんか求めていない」「まちに出て手を差し伸べろ」とずっと言っています。この姿勢は一貫して変わっていないですね。
また、上地市長は議員出身なので議会の気持ちも分かっています。ですから議会とも両輪でうまく進んでいるところが、今の市政の強さだと思います。上地市長以前では、議会が市や市政に対する不信感を抱いていて、なかなか物事がうまく進まなかった時代もあるのですが、そこが今は大きく違うと感じています。
小田 ちなみに、上地市長でなかったとしても今の改革は進みましたか?
寒川氏 いや、ここまで強烈にはいかなかったんじゃないですかね。うちの市長のすごいところって、「条例なんか全部変えていいから」って「君の好きなようにやっていい」と言うのです。それ故結構強めにいけるところが、ありがたい話ですね。
でも多分それは、信用しているから「ちゃんとやれよ」ということの証しだと思いますし、私は私でちゃんと結果を出さなければいけないなと思っています。
小田 なるほど。前回、上地市長にインタビューした際に、精神的には辛いけれども闘い続けなければいけないと仰っていて、組織変革に懸けるリーダーの重責を感じました。特に最初の頃は大変だったみたいで、職員は「なんで言って分からないのだろう」「俺の思いが伝わらないのだろう」と、ずっと悩んだと仰っていました。
寒川氏 今はだいぶ変わってくれたというのを、この間の部長会議で話していましたよ。
組織的な壁を乗り越えるための戦略
小田 デジタル・ガバメント推進室の設立当初は職員の抵抗もあって苦労されたとお聞きしました。
寒川氏 2020年からさまざまな取り組みを進めてきましたが、ゲリラ的な活動では限界を感じました。そこで部署設立時にデジタル・ガバメント推進本部会議を立ち上げました。
自治体組織においては会議体が形骸化しやすいため、副市長に相談し全部局長に「DXについていつまでに何をやるか、各部局で可視化しろ」と明確に宣言してもらうことを考えました。そして21年4月に「本気でやれ」という号令を発してもらいました。
この強いリーダーシップによって、部局長たちの意識が次第に変わり始め、「DXって何?」「何をするの?」という反応が出てきました。本格的に機運の醸成ができたのは、デジタル・ガバメント推進室設置から1年後の21年からでした。現状を打破するため、副市長から強い意志とメッセージを発信してもらうことで大きな波を起こしたのです。
小田 そこでようやく組織が動きだしたのですね。市長や副市長が漠然と指示しても組織は動きにくいものですが、副市長の本気度が影響したのでしょうか?
寒川氏 私がいくら説明しても、現場は「なぜこれをやる必要があるのか」と疑問を持っていました。1年経過しても、DXの重要性を理解していない職員がいることに、市長と副市長は驚いていました。
小田 横須賀市の特徴は、トップがDX推進の必要性を強く認識し、市長と副市長が明確に宣言していたことなのですね。
寒川氏 はい。市長・副市長の方針表明があり、さらに議会も「横須賀市とDX推進を応援する」と表明してくれたので、この両輪で進められました。そのおかげで私も強い姿勢で推進することができました。
(第2回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年6月2日号
【プロフィール】

寒川 孝之(さむかわ・たかゆき)
窓口・福祉部門を経て2001年に情報政策課(情報システム部門)へ配属。ICカードの実証実験「IT装備都市研究事業」を担当。05年に横須賀市コールセンターを開設後、大規模土地利用によるまちづくり事業に従事。
14年から複数回実施された臨時福祉給付金支給業務を統括、17年からオリンピック担当となり、イスラエル柔道チームの事前キャンプ誘致を実現。20年4月、横須賀市経営企画部デジタル・ガバメント推進室長に就任、2024年から現職。