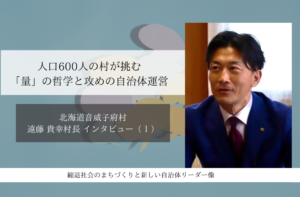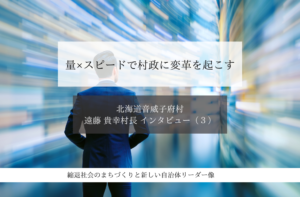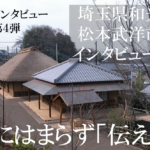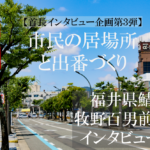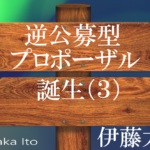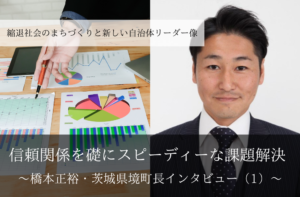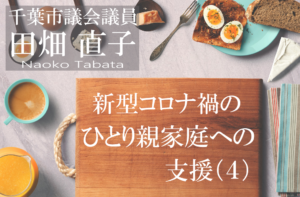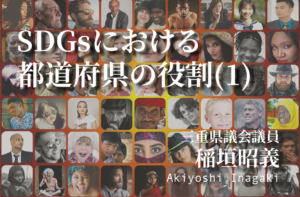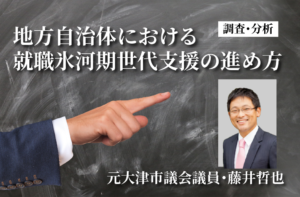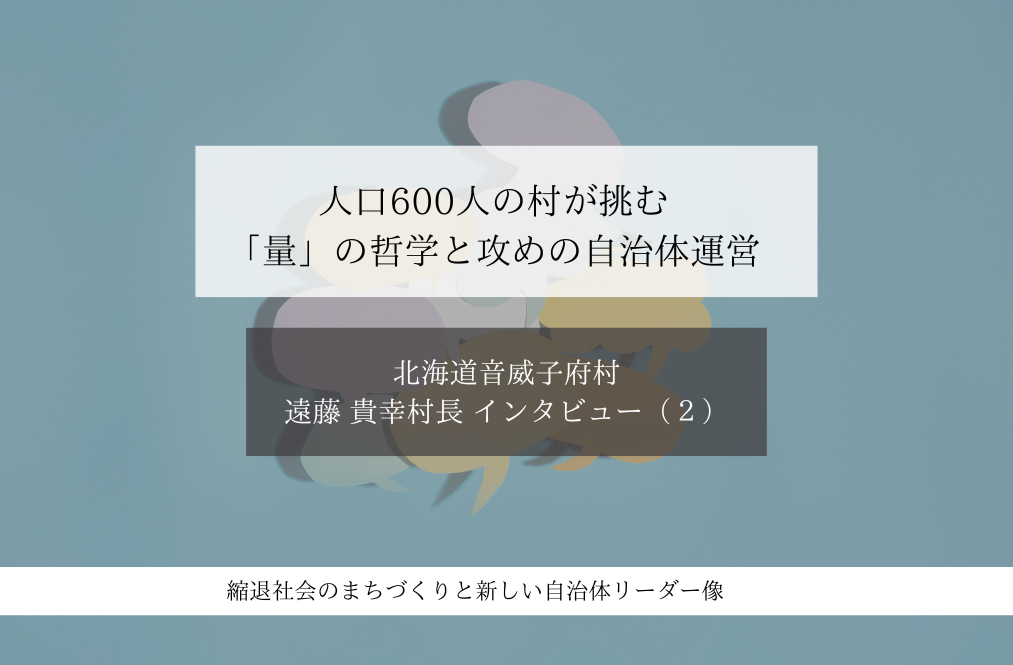
北海道音威子府村長 遠藤貴幸
(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子
2025/10/08 人口600人の村が挑む「量」の哲学と攻めの自治体運営~遠藤貴幸・北海道音威子府村長インタビュー(1)~
2025/10/09 人口600人の村が挑む「量」の哲学と攻めの自治体運営~遠藤貴幸・北海道音威子府村長インタビュー(2)~
2025/10/14 量×スピードで村政に変革を起こす~遠藤貴幸・北海道音威子府村長インタビュー(3)~
2025/10/17 量×スピードで村政に変革を起こす~遠藤貴幸・北海道音威子府村長インタビュー(4)~
行動の「質」より「量」を重視
小田 そうした中で、具体的にどのような連携を進められているのでしょうか。人口減少に悩む他の自治体にとってもヒントになりそうです。
遠藤村長 幾つかあります。例えば「複」村長制度の導入です。これは、自身のスキルアップや地域貢献を望む外部人材と、豊かな経験を村政に活かしたい当村をつなぐ、東京の企業を介したマッチングの取り組みです。4人の「複」村長がボランティアとして無償で活動しており、週に1度のオンラインでの打ち合わせを基本としています。

この制度の背景には、人口が少ない当村のマンパワーだけでは地域の創生が難しいという認識があります。そこで、低コストで外部の多様な視点や専門知識を村政に取り入れることを目的として導入しました。外部人材の経験やスキルを活用することで、マンパワー不足の解消と活性化事業の推進を図っています。
特に期待しているのは、外部の異なる視点から村の隠れた魅力を再発見し、その魅力をさらに引き出すことです。これにより持続可能な地域づくりに貢献できると考えています。この取り組みは、北海道で最も小さな村を、最も元気な村にするという大きな目標に向けた戦略の一環です。
小田 「複」村長制度のような外部との連携を進める一方で、内部の体制づくりも重要になってきますね。外部人材を積極的に活用されることで内部からの反発はなかったのでしょうか。先ほど職員にも熱量が必要とおっしゃっていましたが。
遠藤村長 そうした懸念は当然ありました。改革を進める際には変化が伴います。内部の体制づくりを進める上では、職員との対話を最も重視しています。村政の主役は村民であり、行政の主役は職員だからです。
昨年は若手職員全員とミーティングを行いました。複数でも個人でもどちらでもよいと伝えたところ、ほとんどの職員が個人で話したいと来てくれました。その時に、夢や目標についてざっくばらんな話をしました。明確な目標のない職員もいましたが、それもよいと思います。これから見つければよいのですから。一つ全員に共通して行った質問がありました。「あなたは仕事に対して質と量、どちらを重視しますか?」という問いです。これに対し、成長の見込みのある職員はほぼ全員が「量」と答えました。
小田 「質」ではなく「量」ですか? 一般には「質」が重視される印象ですが。
遠藤村長 これについては私なりの持論があります。若い頃は頭で考えることも重要ですが、どれだけそれをアウトプットして経験に変え、フィードバックを重ねていくかが重要だと思っています。このサイクルを繰り返すかどうかで、20年後、30年後に大きな差が生まれると考えています。
「質」を追求しても、質の評価は主観的なものです。例えば私の仕事をA職員、B職員、C職員が評価した場合、それぞれ異なる評価になるでしょう。自己評価でも「私は質の高い仕事をしている」と思っても、相手からすれば全く評価されていないかもしれません。そこに慢心している職員は、必ず成長が止まります。
私はこの持論に基づき行動してきました。例えば、トライアスロンで北海道1番を目指していたときのことです。練習の質だけでは絶対に勝てないと思っていました。質は数値化できないからです。そこで、目標としていた強豪選手に練習量を聞き、その倍の練習をすれば勝てると逆算して取り組みました。年間1500時間の練習をし、純粋なアマチュア、つまり普段働きながら競技をしている選手の中ではトップレベルに達することができました。
小田 倍ですか。まさに「量」ですね!
遠藤村長 アマチュアのトップレベルでしたから、さすがにプロには勝てませんが、(米ハワイの)アイアンマン世界選手権を目標にしていました。次はいよいよ選手権だと意気込んでいたところ、大会の1カ月半前に骨折しました。このとき心も折れてしまい、次のステップでは何をしようか……としばらく考える時期が続きました。これが政治家を目指すきっかけの一つになりました。
直接的なきっかけは、新型コロナウイルス感染症です。私は村長になる前は27年間消防士を務めていました。米国などでは消防士はヒーローとして扱われていますが、日本では単なる公務員という認識で、評価はそれほど高くありません。私は人を助けるヒーローでありたいと思い働いてきましたが、コロナ禍でエッセンシャルワーカーとして看護師、介護士、医師などが注目される中、第一線で活動する消防士は全くクローズアップされませんでした。個人的にはそれが非常に悲しかったのです。
所属していた消防の団体からも同様の声がありました。結局これは政治を変えなければ解決しないと感じ、政治家への思いが次第に強くなりました。
小田 以前の横須賀市のインタビュー(6月9日号)でも「消防局は『市民の命を守る』という使命感が強い」という話が出ました。時に自分の身を危険にさらしても市民の安全を守ろうとする消防士の方々には、私も心から敬意を抱いています。その使命感こそが、遠藤村長の行政運営の根幹にあるのだと感じます。
遠藤村長 ありがとうございます。私は23年の統一地方選挙で村長になりましたが、その前の19年の時点では有志たちと「誰か立候補して地域を変えてくれないか」と思っていました。しかし結局無投票で時が過ぎました。21年ごろ、再び地域で選挙の話が出たとき、「なぜ自分は政治家になりたいと思いながら、一番お世話になったこの自治体を変えるために自分で行動しないのか」と考えました。後ろ盾は何もありませんでしたが、いずれ政治家になろうと思っているなら今だと考え、立候補を決めました。
従来配布されていた村政に関するリーフレットには「住んでよかった村にします」と書いてありますが、「どうやって?」と思っていました。だから私は住民から直接要望を聞き、4年間で何をするかをマニフェストとして具体的に示しました。現在、その7割程度は達成していると思います。
行動量を定量的な成果へ
小田 実行力のある首長の方は、4年間の計画をご自身の中で明確にしている方が多いですね。具体的な政策を掲げて、それを着実に実現されているというのは素晴らしいと思います。
遠藤村長 これまで小中学校になかった給食を配食という形で開始しました。就任前は学童保育もありませんでしたが、これも2年目の4月に設置しました。学童に関しては10年以上前から要望があったにもかかわらず、行政は何も動いていませんでした。だから速やかに実行に移しました。
その後、地域おこし協力隊の活用と、村役場職員の副業を明確化しました。次に、足りない資金と人材、知見を外部から調達する官民連携に取り組みました。「複」村長は複業クラウドサービスで募集し、90人程度の応募から選考しました。その方には現在、地方創生アドバイザーとして東京の企業案件の窓口を担ってもらっています。
小田 八面六臂のご活躍ですね。
遠藤村長 まだ十分な成果が出ているとは考えていません。私が重視しているのは、定性的な「住んでよかった」ではなく、定量的な成果です。
現在、企業と連携して「音威子府村1000人プロジェクト」という10年計画を検討しています。現在600人の村を10年後に1000人にする計画です。減少することを前提とせず、増加だけを考える発想です。現在の600人から400人増やせば1000人になる。人口減少対策ではなく、人口増加対策を進めたいと考えています。
小田 斬新なアプローチです。
遠藤村長 そのための移住対策についても積極的に考えています。世の中には、東京に住所がなくても仕事ができる人材がたくさんいます。そうした方々に移住していただき、まずは当村に住民票を置いてもらう──こうした政策も一つの手法だと考えています。もちろん、他の自治体からは反発もあるでしょうが、現在は自治体も積極的に打って出なければ生き残れない時代です。
小田 従来の枠組みを超えた発想ですね。
遠藤村長 上川管内では「音威子府のために」と先輩首長の皆さまが言ってくださり、全国初の自治体総合包括連携で「みんなで助け合おう」と進めている最中に、私が「自治体間の競争は避けられない時代です。限られた人材も資金も、積極的に獲得していかなければ」と言っているわけです。もちろん、全てを競争で解決するわけではありません。連携すべき部分では協力し、一方で人材確保や企業誘致など競争が避けられない分野では積極的に取り組む。このメリハリが重要だと思います。
地方が衰退すれば、東京も必ず影響を受けますから、もう少し分散してほしいと思います。1000人プロジェクトがある程度軌道に乗れば、逆転現象も起きてくるでしょう。地方の活性化は、結果的に日本全体の持続可能性を高めることにつながると考えています。
小田 具体的にはどのような取り組みを進められているのでしょうか。
遠藤村長 現在取り組んでいるのは王道の手法です。移住定住促進として空き家バンクの活性化、企業誘致も進めています。企業誘致については数を打つことをとにかく意識しています。1回でうまくいかなければ10回、100回、1000回挑戦する。1000回も挑戦すれば一つか二つは成功するでしょう。
重要なのはスピード感です。意思決定を含めた迅速性、そしてトラブルへの迅速で最善の対応姿勢や行動力が最も大切だと思っています。企業との連携でも「こういう問題が発生しました」と報告があれば即座に対応し、100%解決できなくても合格点まで到達させることで、相互の信頼関係が構築されるでしょう。このように、行動量の中から成果を生み出すことを考えています。
小田 遠藤村長の自由度の高い発想とスピード、そして行動量に感銘を受けたインタビューでした。
次回以降も、政治哲学や地域を盛り上げるための施策を具体的に伺います。
(第3回に続く)
※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年9月1日号
【プロフィール】

遠藤 貴幸(えんどう・たかゆき)
北海道中川郡中川町出身。
元北海道上川北部消防音威子府支署長。
2023年の統一地方選挙にて当選し音威子府村長に就任。
現在1期目。趣味は筋トレ・ランニング・サイクリング・水泳など。