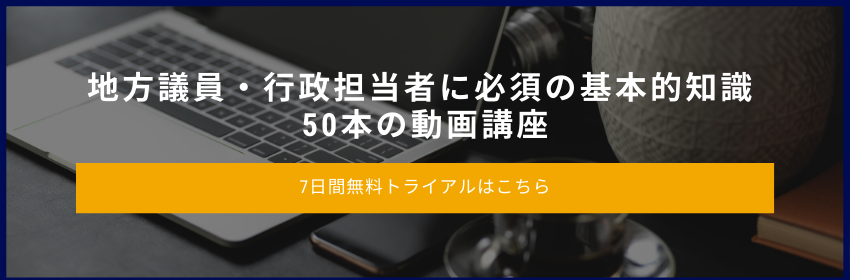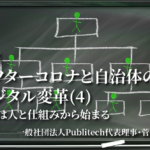前回は21世紀初頭にエレクトロニクス産業が直面した垂直統合から水平分業への産業構造の変化が、これから自治体の都市経営にもやってくる、そんな時代に差し掛かっていることをお伝えしました。
第2回の今回は、暮らしの中に見えるオープン化と公共サービスで始まりつつあるオープン化について取り上げます。
水平分業は「オープン化」とも呼びます。要は自前主義からの脱却です。繰り返しますが、オープン化の流れは何もエレクトロニクス業界をはじめとする、産業界に限った話ではありません。
私たちの暮らしの中にある、オープン化を見てみましょう。例えば、スーパーやデパートなどで売っているお惣菜。2018年5月の日本経済新聞によると、中食の市場規模は10兆円を超え、私たちの暮らしにおけるオープン化の代表的な例です。専業主婦が作るのが当たり前だった家事の一部が、サービスとして提供されるようになったのが中食だからです。
その背景には共働き世帯の増加といった、ライフスタイルの変化が大きく影響しているのは周知の通りでしょう。かつての標準世帯モデルでは男性が外で働き、女性は専業主婦として家事の一切合切を請け負うというライフスタイルだったのが、共働きがスタンダードになったことで、家事は分担、それもできれば省力化したいという流れの中で、調理されたものを購入して家で食べるというスタイルが根付いたわけです。つまり調理という機能を家庭から外部へアウトソースした形です。
こうした例は枚挙にいとまがありません。しかもテクノロジーの進化によってオープン化の波は暮らしから公共サービスとあらゆる分野に及んでいきます。私たちは今、まさにそのとば口に立っています。
さて、社会のオープン化というものが公共サービスをどのように変えていくのか、その中で必ず出てくるオープンイノベーションとどう向き合っていくのか、といった点について論考していきましょう。
巷間言われていることですが、少子化・高齢化による生産性の低下は自治体財政に大きな影響を与えています。現状でさえ財政難にあえいでいる自治体が多い中、従来のようにすべての行政サービスをフルセットで維持するのは難しくなるのは必至です。
ここ10年を振り返っても、指定管理者制度からPFI、PPPと様々な公民連携の手法が採用されてきたのは、基本的にオープン化の文脈にあると言っていいでしょう。財政的な理由から、自前主義でやるのが困難になり、これまで自治体が担っていた行政サービス、機能を企業に担ってもらおう、というものだからです。
社会の変化を前に「べき論」は無意味
PFI/PPPに代表される公共サービスのオープン化は今なお進行中ですが、やはり、導入当初は市民や議会の抵抗も大きかったのは記憶の通りです。もっとも分かりやすい批判は「税金で整備したものを一企業の収益事業として任せていいのか」といったものでした。
この批判は一見、もっともらしく聞こえます。私自身も議員になりたてのころは、このように考えていた時期もありました。しかし、結局、背に腹は変えられないという身も蓋もない話に行き着きます。今の財政状況では自前主義では公共サービスの維持は不可能だから、です。
前述した専業主婦モデルから夫婦共働きモデルへと家庭の状況が変化したことにともなって、家事のアウトソースが進行し、中食というビジネスが大きく成長したのと同じです。そこには「女性は家庭で家事をすべきである」といったイデオロギーともいうべき昭和的価値観、あるべき論は意味をなしません。家事を一部でもアウトソースしないと、家庭そのものが回らない状況になっているからです。自治体における公共サービスのオープン化も基本的には同じです。
ただ1つ違う点があリます。オープン化といっても、完全な経済論理だけでは回せないという点です。自治体が提供する行政サービスは基本的には「市民の福祉」のため。したがって、自治体がサービスや機能を自前で担えないから企業に担ってもらうのは仕方ないとしても、企業の論理を全面に押し出されてしまうと、なかなか難しいわけです。本来行政サービスは市民の福祉である以上、企業活動における費用対効果の考え方をストレートに反映するのは市民からの反発も出やすくなります。
公共サービスのオープン化に求められる行政のクリエイティブ
これからの行政の役割は、企業が望む経済活動と市民の福祉が両立するいい塩梅を見つけ、そういう運用になるような仕組みをつくることです。行政職員に求められる創造性と言ってもいいでしょう。
今後、増えるのは、経済活動と市民の福祉の均衡点のデザインがもっとも難しい公園や河川、図書館などでの公民連携です。こうした公共施設・公共空間は関わるステークホルダーが多く、要求される機能が高度です。いずれも従来無料で使うことのできた空間であり、施設でもあります。
そこの運営を企業が担い、公園の維持管理費を生み出すために、その一部を使って収益事業を展開するとき、批判が起きる可能性は大いにあります。今まで無料で使えていた場所が、常時か、イベント時だけかという利用形態の違いはあったとしても、経済活動に使われることへのアレルギー反応が起きることは容易に想像できることです。そうなっては企業にとってはブランド・イメージの毀損にもなりかねません。
そこで重要になってくるのが、オープンイノベーションという手法です。その定義については、本稿冒頭に触れた通りで、「異なる分野の技術やアイデア、ノウハウ、データを持ち寄って、新しいサービス、商品を開発すること」。
さて、次回第3回は、テクノロジーが後押しする都市のオープン化について取り上げます。
(株式会社Public dots & Company 伊藤大貴)